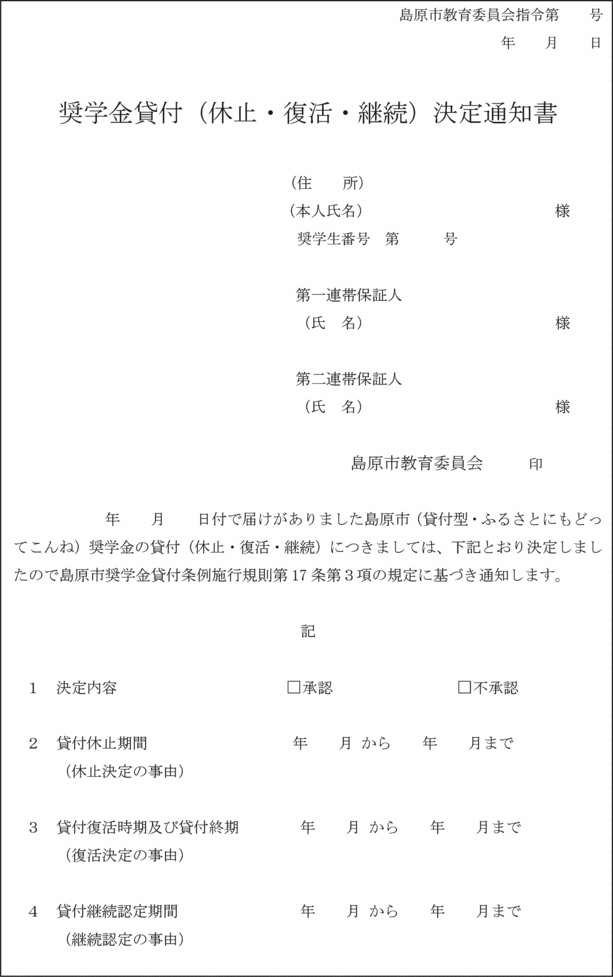○島原市奨学金貸付条例施行規則
平成29年2月1日教育委員会規則第1号
島原市奨学金貸付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市奨学金貸付条例(平成29年島原市条例第2号。以下「条例」という。)第21条の規定により、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(奨学金の対象者の要件)
第3条 条例第5条第3号又は条例第15条第3号に該当する者は、条例第3条に規定する奨学金の貸付を希望する者(以下「申請者」という。)の家計支持者(原則として法定代理人とする。)の前年の収入金額を基礎として算出した総所得金額が、教育委員会が別に定める基準以下である者とする。ただし、条例第9条の奨学生審議委員会(以下「審議委員会」という。)又は条例17条のふるさとにもどってこんね奨学生審議委員会(以下「ふるさと審議委員会」という。)の審議を経て教育委員会が特に認める場合はこの限りでない。
2 条例第5条第4号に該当する高校等及び大学等の出願者は、それぞれ次の各号を満たす者とする。ただし、審議委員会の審議を経て教育委員会が特に認める場合はこの限りでない。
(1) 高校等の出願者 中学校又は高校等の学習成績の評定(5段階評価)の平均値が3.0以上
(2) 大学等の出願者 第1学年に在学する者は、高校等の学習成績の評定(5段階評価)の平均値が3.5以上、第2学年以上に在学する者は、在学する大学等の学習成績が教育委員会が別に定める基準以上
3 条例第15条第4号に該当する出願者は、高校等の学習成績の評定(5段階評価)の平均値が4.0以上の者とする。ただし、ふるさと審議委員会の審議を経て教育委員会が特に認める場合はこの限りでない。
(連帯保証人)
第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、2人の連帯保証人(以下「保証人等」という。)を立てなければならない。
2 保証人等のうち第一連帯保証人は、本人の父母、兄弟又はこれに代わる者(当該学生の法定代理人)でなければならない。
3 第二連帯保証人は、本市に住所を有する成人で独立の生計を営み、かつ、保証能力を有すると教育委員会が認める者でなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合には、市外居住者とすることができる。
4 保証人等は、奨学金の償還に関する一切の責任を負い、かつ、身元を保証しなければならない。
(奨学生の申請)
(1) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(2) 高校等又は大学等に在学することを証明する書類
(3) 申請者及び申請者と生計を一にする者の住民票謄本及び所得証明書
(4) 申請者及び申請者と生計を一にする者の市税の滞納がないことを証明する納税証明書(様式第3号)
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(審議委員会)
第6条 審議委員会及びふるさと審議委員会に、それぞれ委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 各委員長は、審議委員会又はふるさと審議委員会を招集し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審議事項)
第7条 審議委員会は、次の各号に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 条例第10条の規定による奨学生の資格決定等
(2) 条例第13条の規定による奨学金の償還猶予
(3) 条例第14条の規定による奨学金の償還免除
(4) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付に関する必要な事項
2 ふるさと審議委員会は、次の各号に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 条例第15条の規定によるふるさと奨学生の資格決定等
(2) 条例第18条の規定によるふるさと奨学金の償還猶予
(3) 条例第19条の規定によるふるさと奨学金の償還免除
(4) 前各号に掲げるもののほか、ふるさと奨学金の貸付に関する必要な事項
3 審議委員会及びふるさと審議委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは各委員長がこれを決する。
(奨学生の決定)
(誓約書等の提出)
(貸付対象期間の延長)
第10条 教育委員会は、条例第7条第2項の規定により奨学生が正当な理由で休学したときその他やむを得ない理由があるときは、奨学生の申出により、貸付対象期間を延長することができる。
2 前項の申出は、保証人等と連署した奨学金貸付対象期間延長願(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の奨学金貸付対象期間延長願が提出されたときは、その内容を審査し、必要と認めるときは、休学等の期間の貸付を休止し、貸付対象期間を延長することができる。
4 教育委員会は、前項の規定により貸付対象期間の延長を決定したときは奨学金貸付対象期間延長決定通知書(様式第8号)により、本人又は保証人等に通知するものとする。
(奨学金の交付)
第11条 奨学金は、原則として毎年度4月、7月、10月及び1月の4期に分けて、本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(資格の取消しの通知)
(在学証明書等の提出)
第13条 奨学生は、毎年度(奨学生に採用された年度を除く。)4月末日までに、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 在学証明書
(2) 前年度の学業成績証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(借用証書等の提出)
第14条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付を受けた奨学金について保証人等が連署した奨学金借用証書(様式第10号)及び奨学金償還明細書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 奨学金の貸付期間が満了したとき。
(2) 奨学生の資格を取り消されたとき。
(3) 奨学金の貸付を辞退したとき。
(4) 死亡又は失踪したとき。
2 前項の保証人等は、原則として誓約書に連署した者とする。
3 本人が死亡、失踪又は疾病等の理由により届け出ることができないときは、相続人又は保証人等が届け出なければならない。
(償還の猶予)
第15条 条例第13条又は条例第18条の規定に基づき奨学金の償還の猶予を申し出る者は、奨学金償還猶予願(様式第12号)を教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出し承認を得なければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により奨学金償還猶予願の提出があったときは、これを審査し、その結果を奨学金償還猶予決定通知書(様式第13号)により本人又は保証人等に通知するものとする。
3 条例第13条又は条例第18条の規定に基づく災害、負傷又は疾病その他やむを得ない事情により償還が困難な場合の猶予期間は、猶予決定の日から1年以内とし、更にその事情が継続するときは、奨学金償還猶予期間延長願(様式第14号)により重ねて1年ずつ延長することができる。ただし、猶予期間は、通算して5年を限度とする。
4 教育委員会は、前項の奨学金償還猶予期間延長願が提出されたときは、その内容を審査し、償還猶予期間の延長を決定したときは、奨学金償還猶予期間延長決定通知書(様式第15号)により、本人又は保証人等に通知するものとする。
6 条例第18条第4号に規定するその他教育委員会が特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その猶予期間は、それぞれ当該各号に定める期間を限度とする。この場合において、当該各号に定める期間は、それぞれ当該各号に定める事由による猶予期間を通算した期間とする。
(1) 就業先の倒産等により離職した場合 1年
(2) 奨学生の責めによらない理由により、就業先から解雇され離職した場合 1年
(3) 奨学生が転職するために離職した場合 1年
(4) 災害、負傷又は疾病により離職した場合 第3項に規定する猶予期間に準ずる期間
(5) その他教育委員会が特に必要があると認める場合 教育委員会が必要と認める期間
8 条例第13条又は条例第18条の規定に基づき償還の猶予を受けた者は、猶予期間中に猶予要件を欠くこととなったときは、奨学金償還猶予要件喪失届(様式第17号)により速やかにその旨を教育委員会に届出なければならない。
9 教育委員会は、前項の届出を受けたときは、奨学金償還猶予取消決定通知書(様式第18号)により、本人又は保証人等に通知するものとする。この場合において、償還の猶予を受けた者は、当該要件を欠くこととなった日の属する月の翌月から貸付を受けた期間の2倍に相当する期間内に月賦又は半年賦の方法で全額を償還しなければならない。
(償還の免除)
第16条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金の償還未済額について免除を願い出るときは、条例第14条又は条例第19条の規定に基づき、奨学金償還免除願(様式第19号)を教育委員会に提出し承認を得なければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により奨学金償還免除願の提出があったときは、これを審査し、その結果を奨学金償還免除決定通知書(様式第20号)により本人又は保証人等に通知するものとする。
(1) 市内又は市外に主たる事業所を有する法人又は団体において就業する者(短時間労働者(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条第3項に規定する短時間労働者をいう。))その他教育委員会が定める者を除く。
(2) 市内又は市外において個人で農業、林業その他の事業を営む者又はその事業専従者(所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第3項に規定する事業専従者をいう。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会がこれらに相当すると認める者
6 条例第19条第3号に規定するその他教育委員会が特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第18条第3号の猶予期間が通算して5年を超える場合
(2) その他教育委員会が特に必要があると認める場合
7 教育委員会は、第2項の審査の際、必要と認めるときは審議委員会に諮るものとする。
(異動届出)
第17条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、保証人等と連署して速やかに当該各号に定める書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 休学したとき 休学届及び奨学金貸付休止願(様式第21号)
(2) 復学したとき 復学届及び奨学金貸付復活願(様式第22号)
(3) 転学したとき 転学届及び奨学金継続願(様式第23号)
(4) 退学したとき 退学届(様式第24号)
(5) 奨学生を辞退するとき 奨学金貸付辞退届(様式第25号)
(6) 本人又は保証人等の住所、姓名に変更があったとき 住所(姓名)変更届(様式第26号)
(7) 本人が死亡又は失踪したとき 奨学生死亡(失踪)届(様式第27号)
(8) 保証人等が死亡又は保証人等としての資格を欠いたとき 保証人等変更届(様式第28号)
2 本人が死亡、失踪又は疾病等の理由により届け出ることができないときは、相続人又は保証人等が届け出なければならない。
3 教育委員会は、第1項第1号から第3号までの申出について、決定をしたときは、奨学金貸付(休止・復活・継続)決定通知書(様式第29号)によりその旨を通知し、当該決定の日の属する月の翌月からその措置を行うものとする。
(貸付対象者の要件を証明する書類の提出)
(準用)
第19条 第2条から第5条まで及び第8条から前条までの規定は、ふるさとにもどってこんね奨学金の貸付について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条見出し、第4条、第11条(見出しを含む。)、第14条、第15条及び第16条 | 奨学金 | ふるさとにもどってこんね奨学金 |
第5条見出し、第8条(見出しを含む。)、第9条、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条、第17条及び第18条 | 奨学生 | ふるさとにもどってこんね奨学生 |
第15条及び第16条 | 審議委員会 | ふるさとにもどってこんね審議委員会 |
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(島原市奨学金貸付基金条例施行規則の廃止)
2 島原市奨学金貸付基金条例施行規則(平成17年教育委員会規則第16号)は、廃止する。
(島原市奨学金貸付基金条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の規定は、この規則の施行日以後に奨学生となる者から適用し、同日前に奨学生となっている者については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月12日教委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月3日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年度の申請に係る奨学金から適用する。
附 則(令和6年4月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
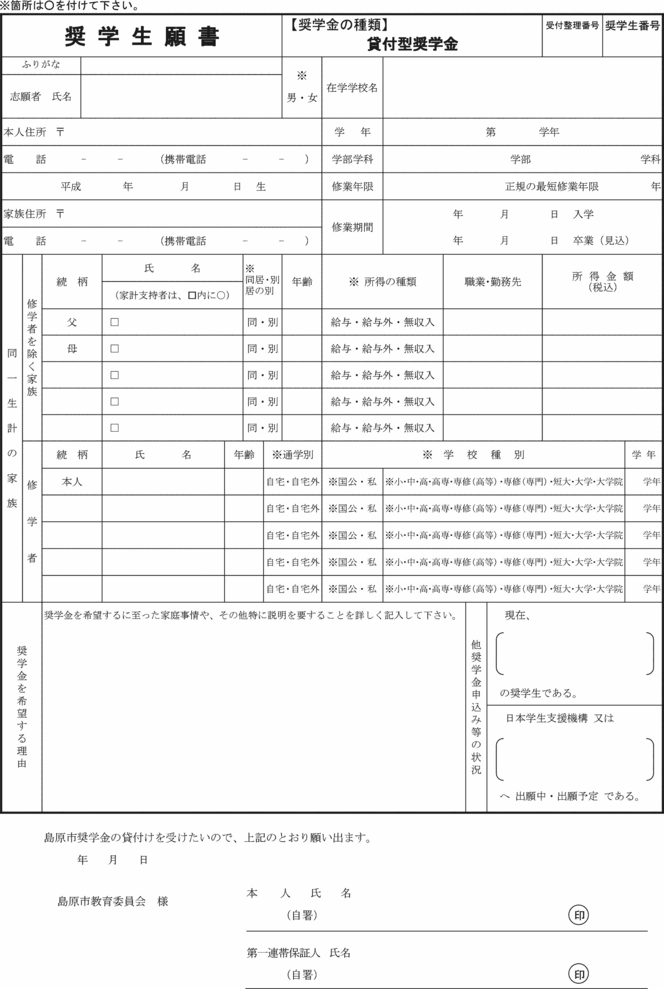
様式第1号の2(第5条関係)
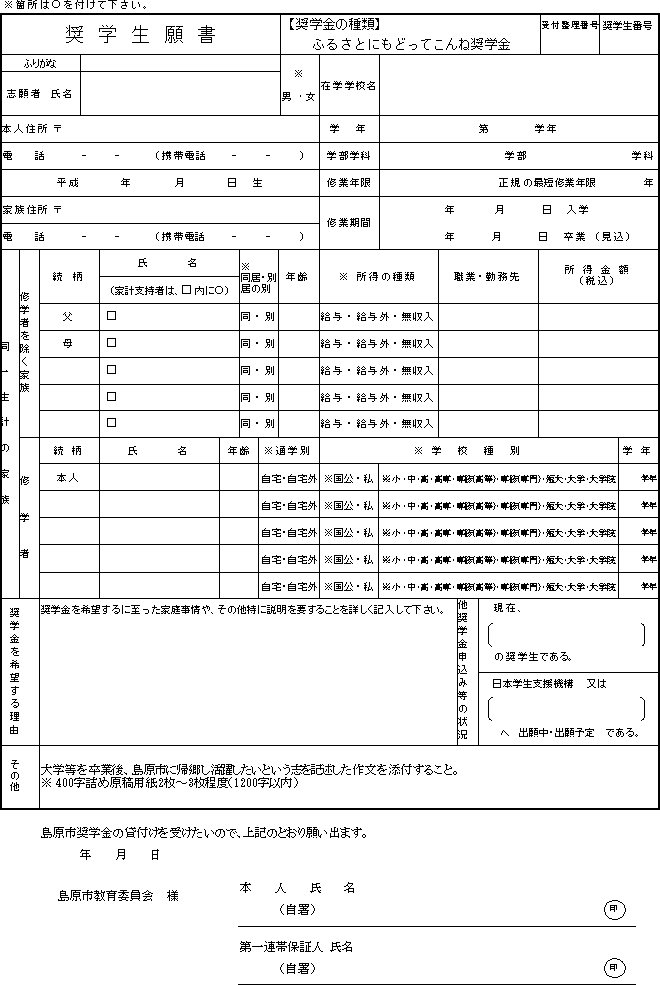
様式第2号(第5条関係)
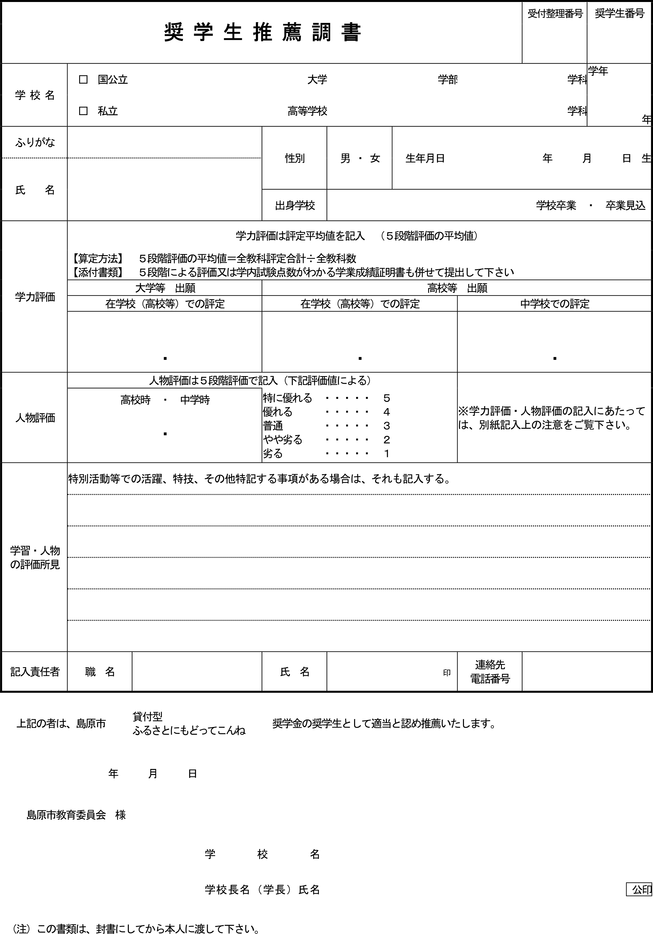
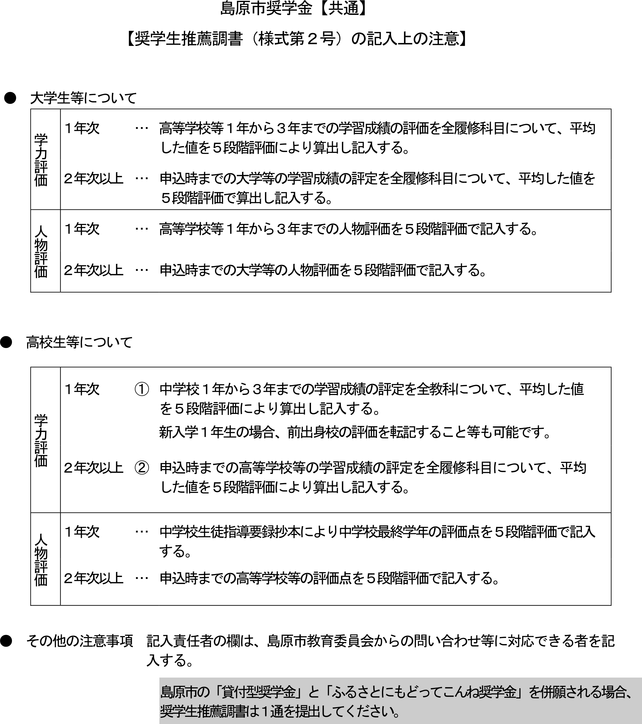
様式第3号(第5条関係)
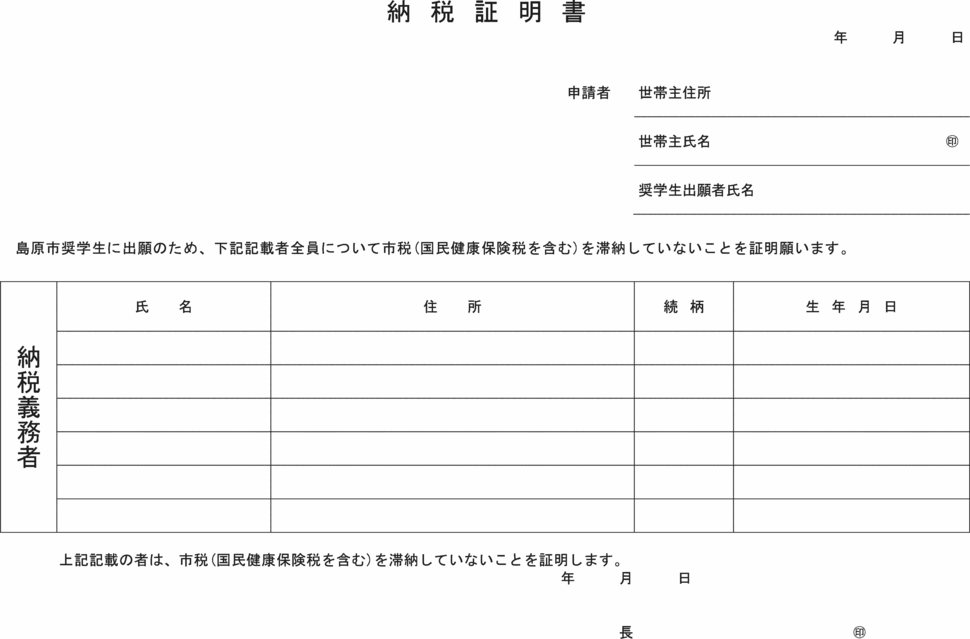
様式第4号(第8条関係)
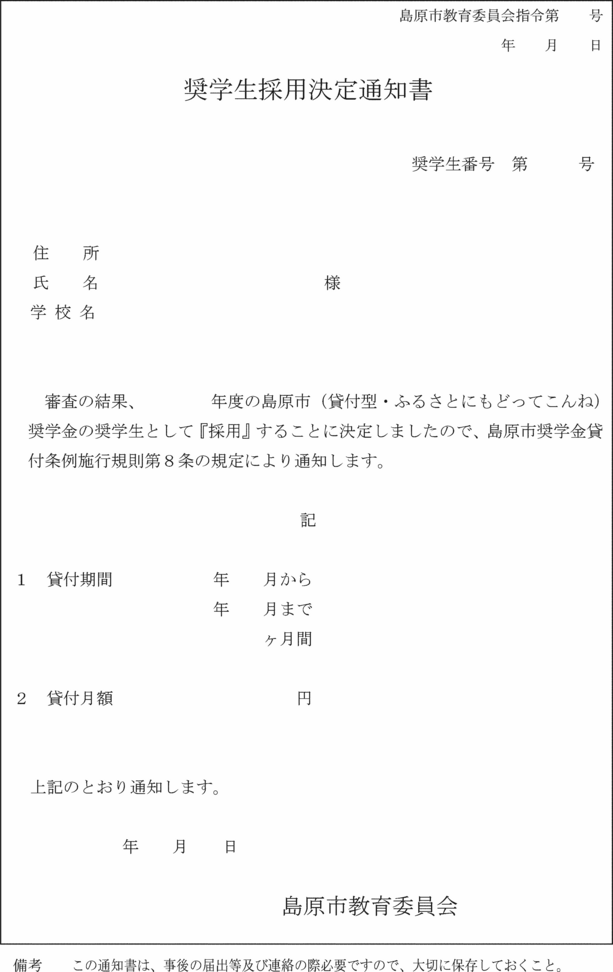
様式第4号の2(第8条関係)
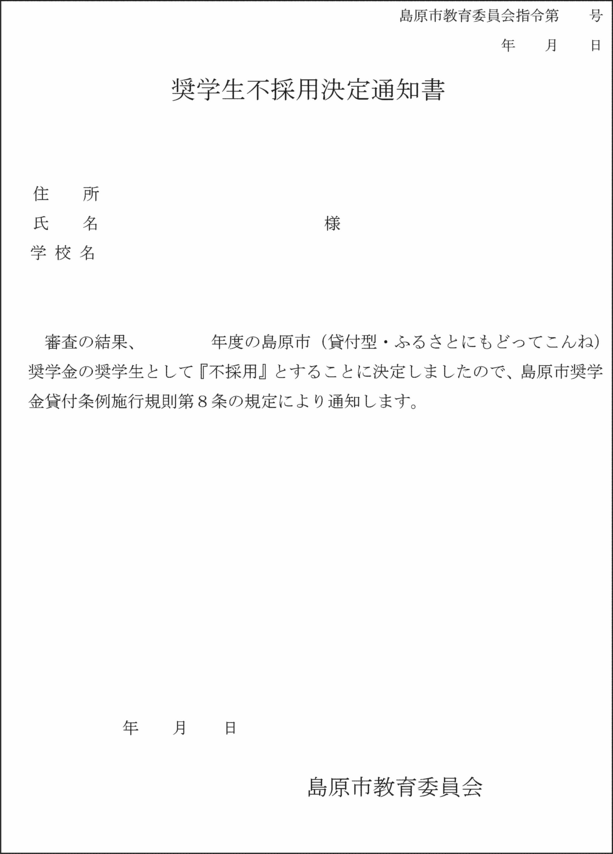
様式第5号(第9条関係)
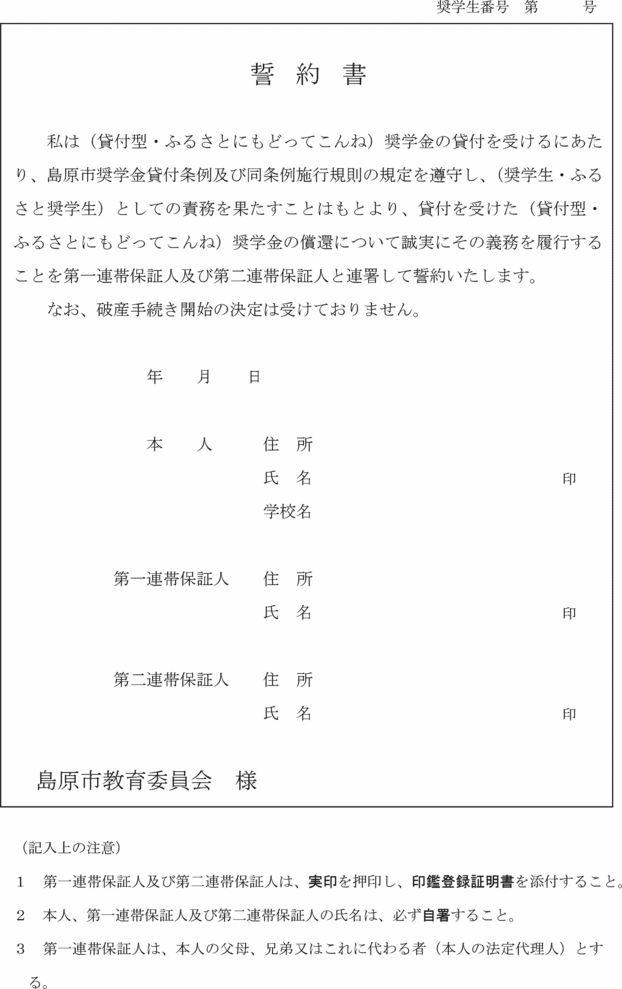
様式第6号(第9条関係)
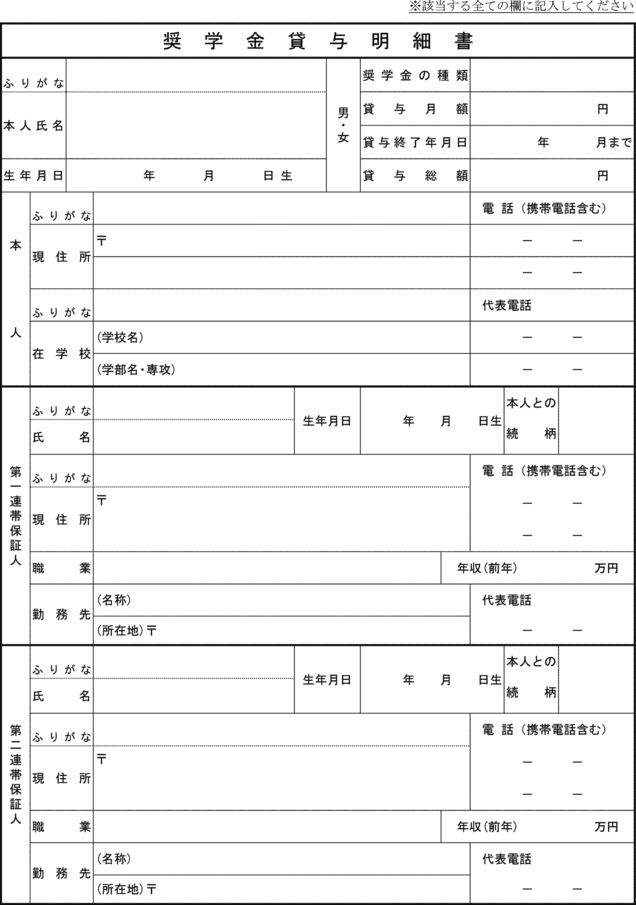
様式第7号(第10条関係)
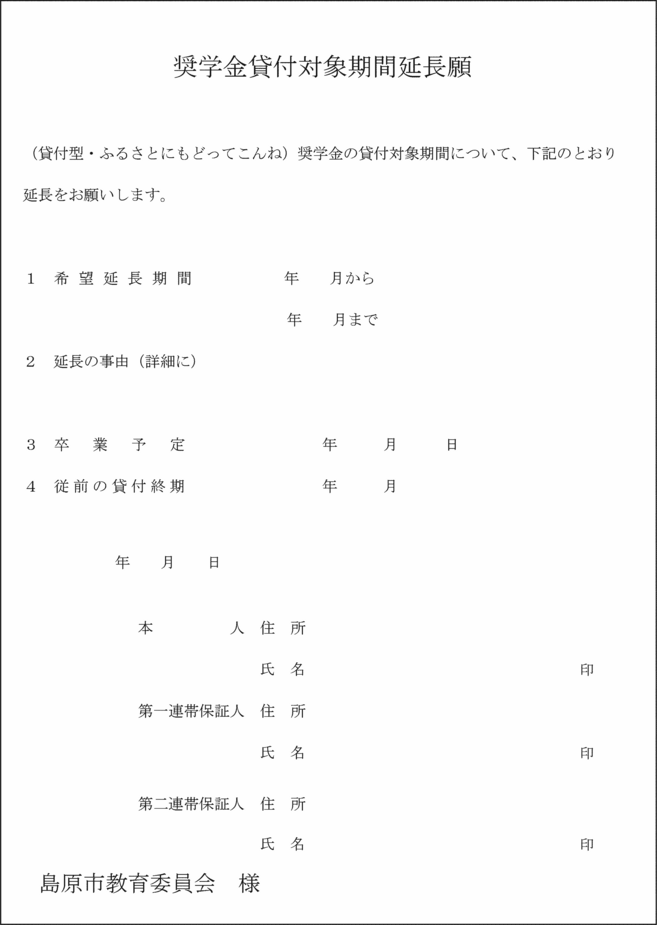
様式第8号(第10条関係)
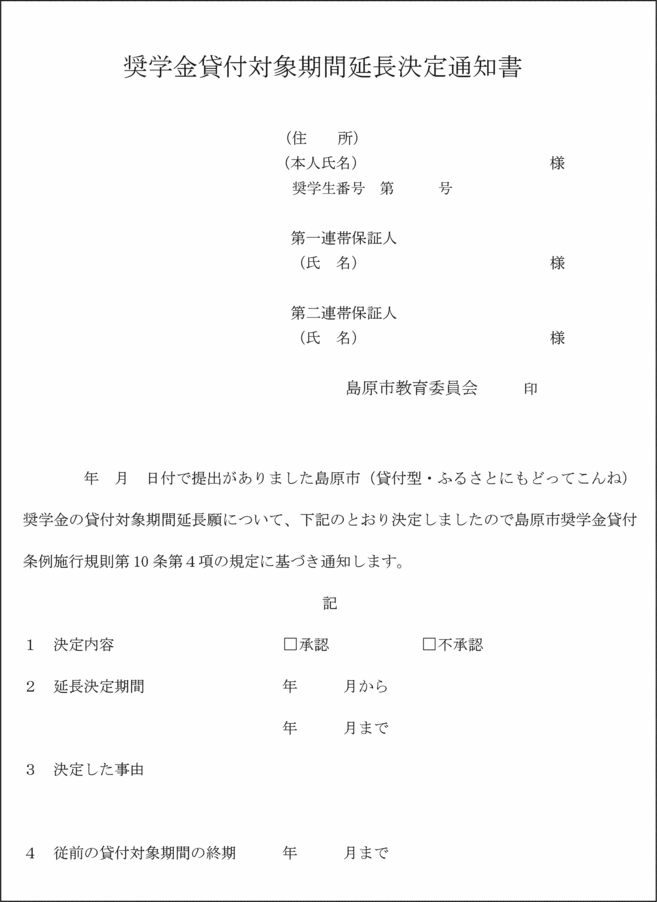
様式第9号(第12条関係)
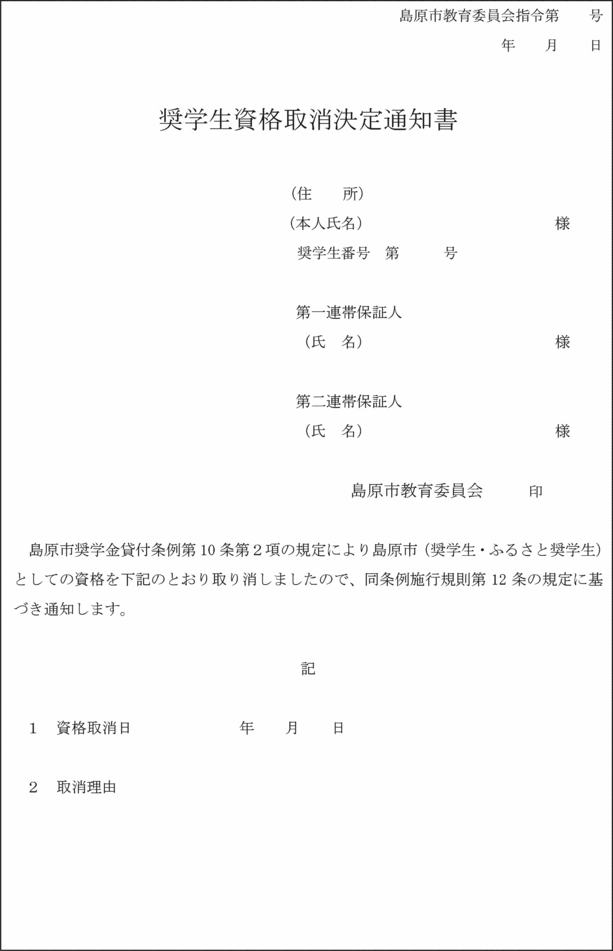
様式第10号(第14条関係)
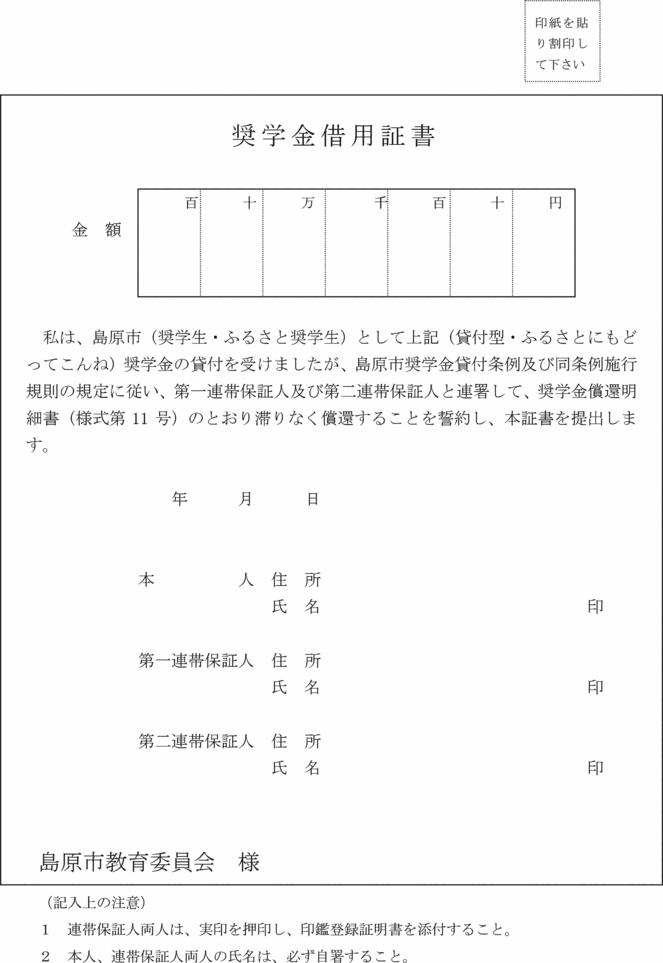
様式第11号(第14条関係)
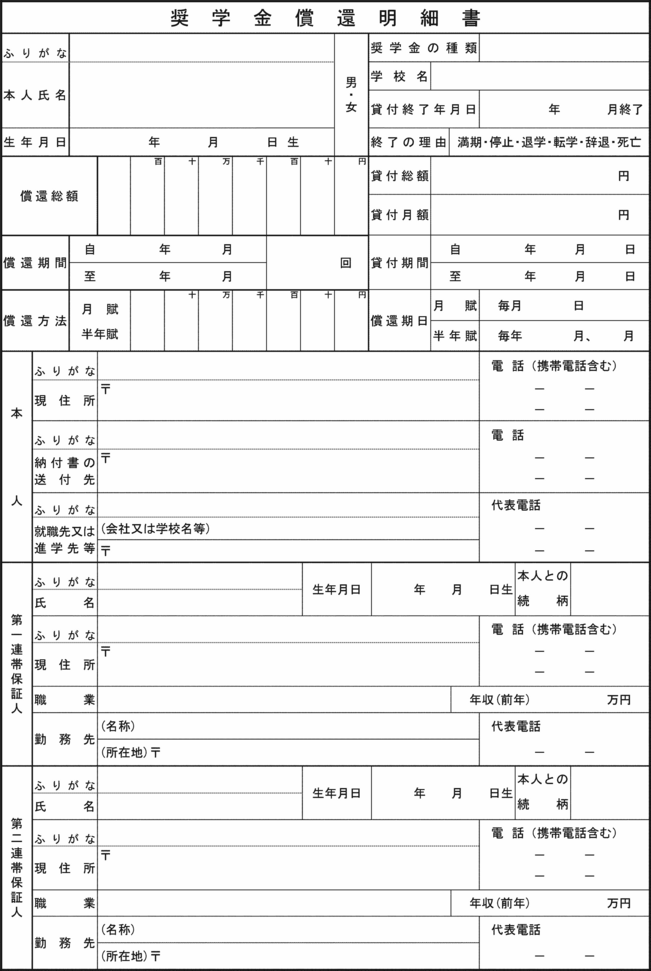
様式第12号(第15条関係)
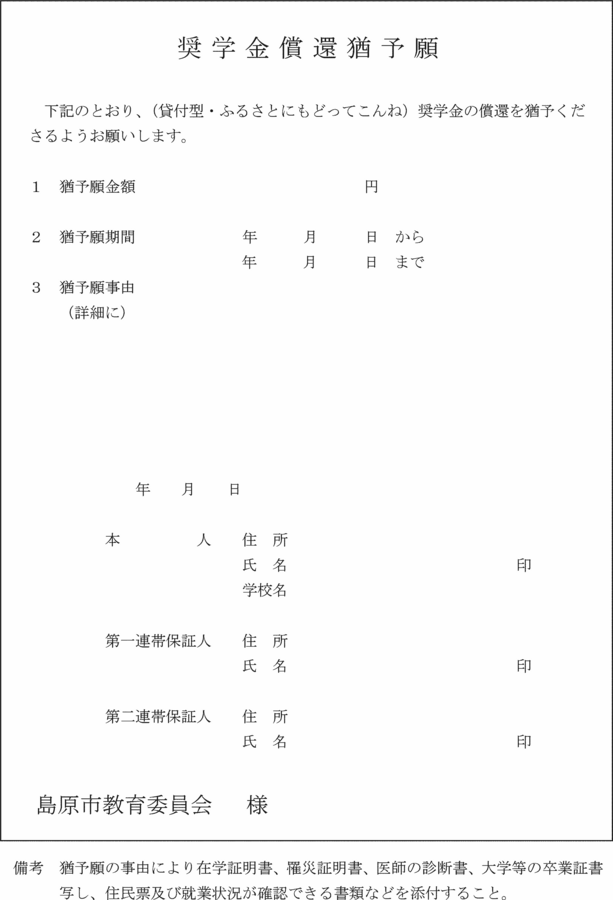
様式第13号(第15条関係)
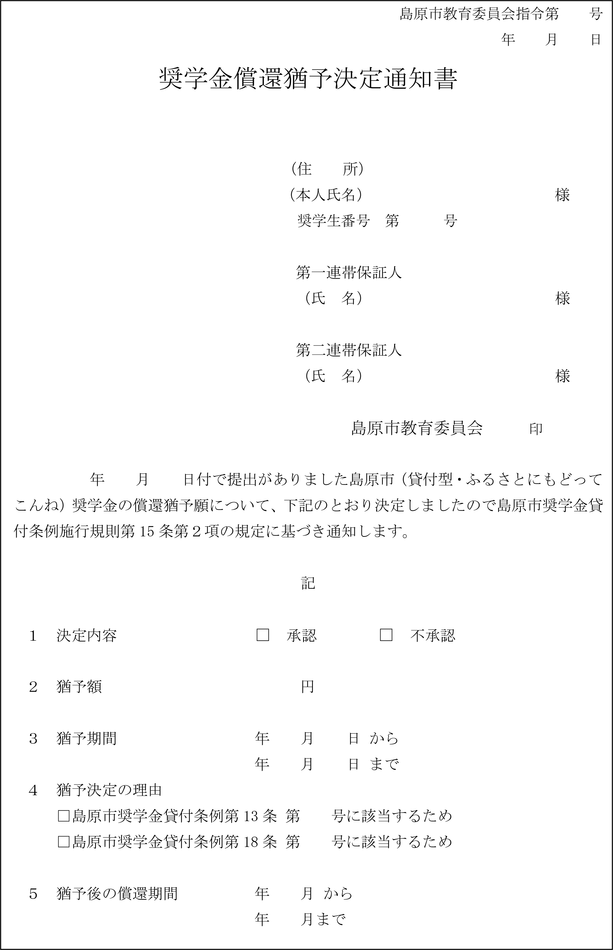
様式第14号(第15条関係)
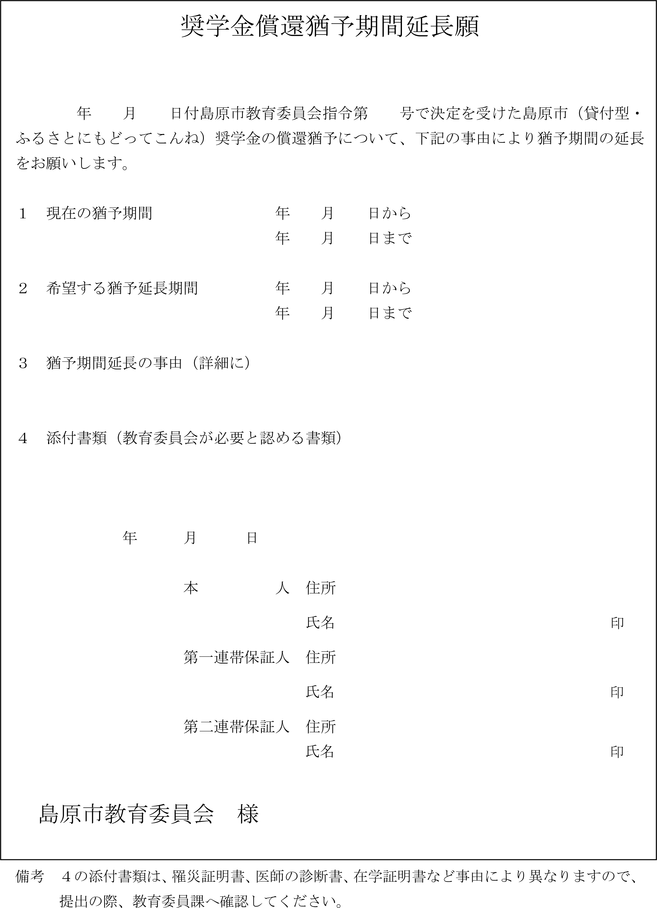
様式第15号(第15条関係)
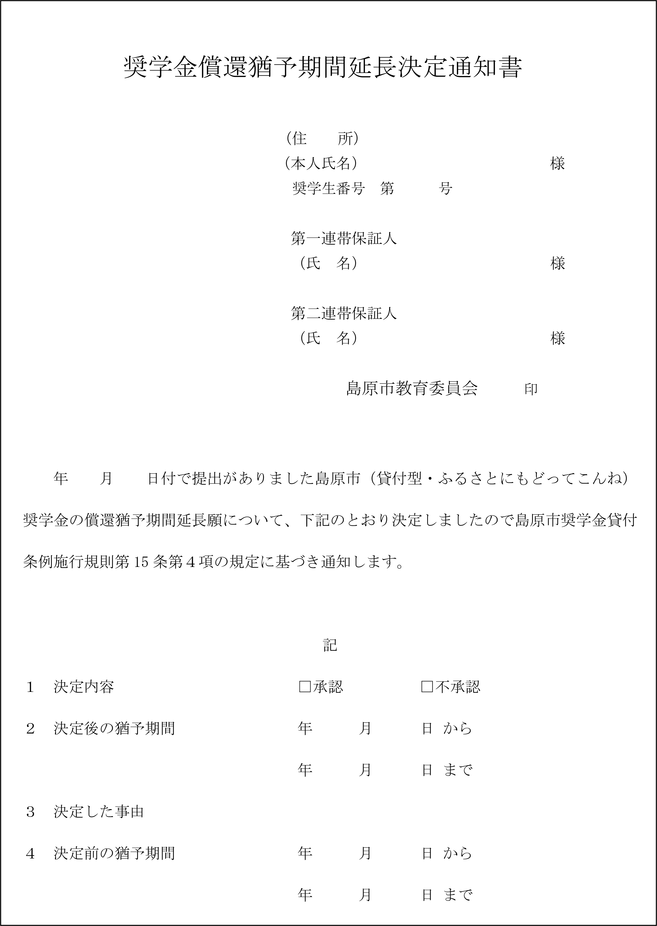
様式第16号(第15条関係)
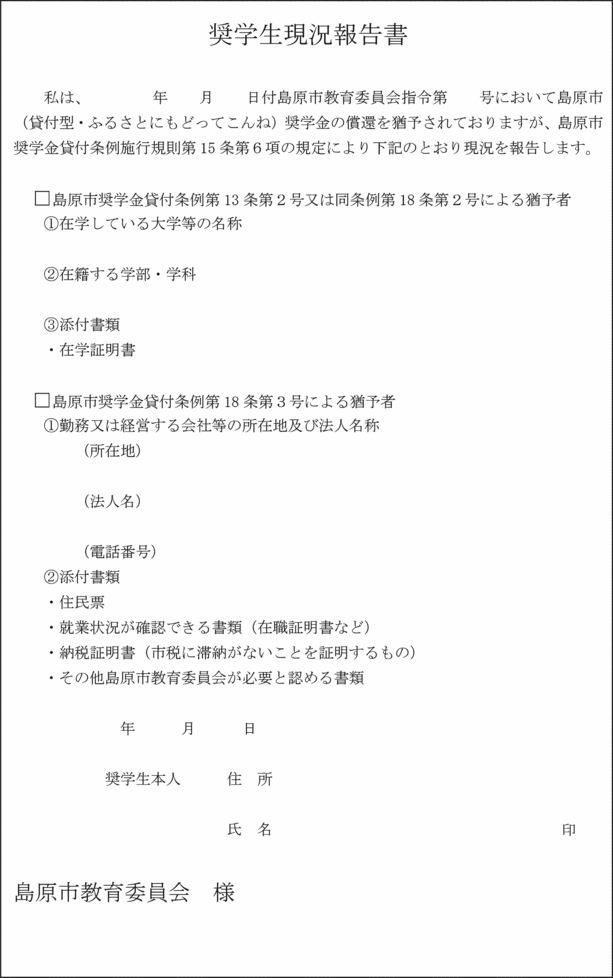
様式第17号(第15条関係)
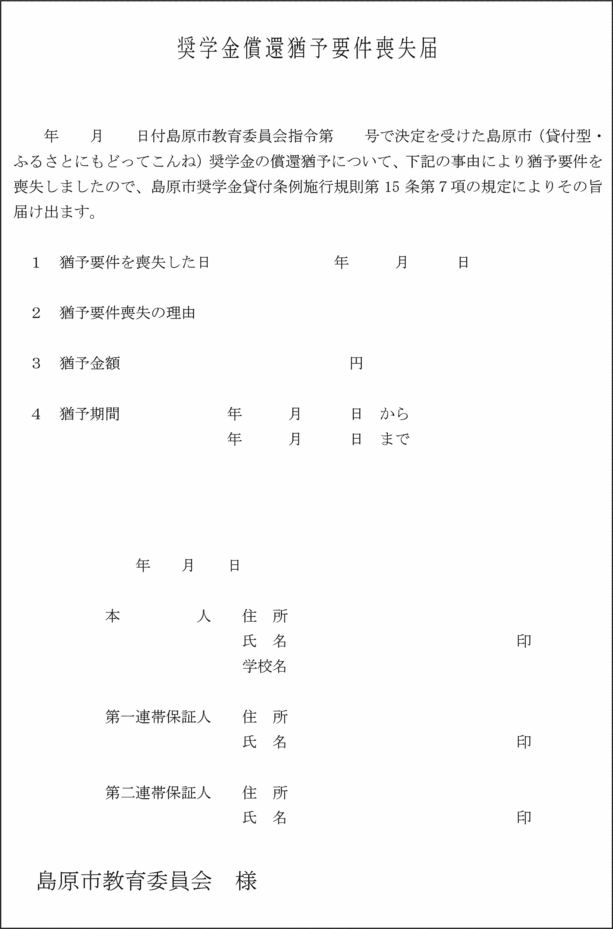
様式第18号(第15条関係)
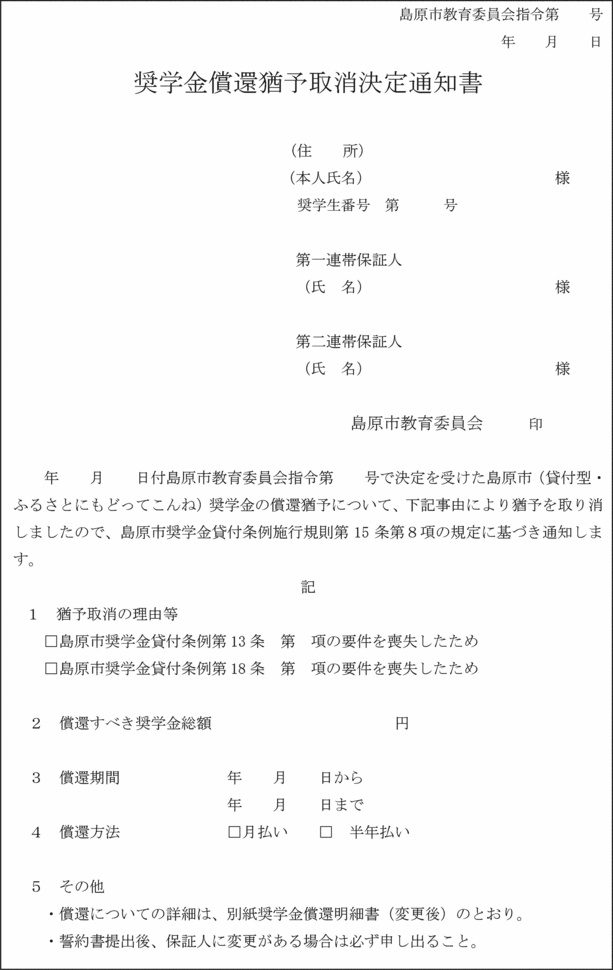
様式第19号(第16条関係)
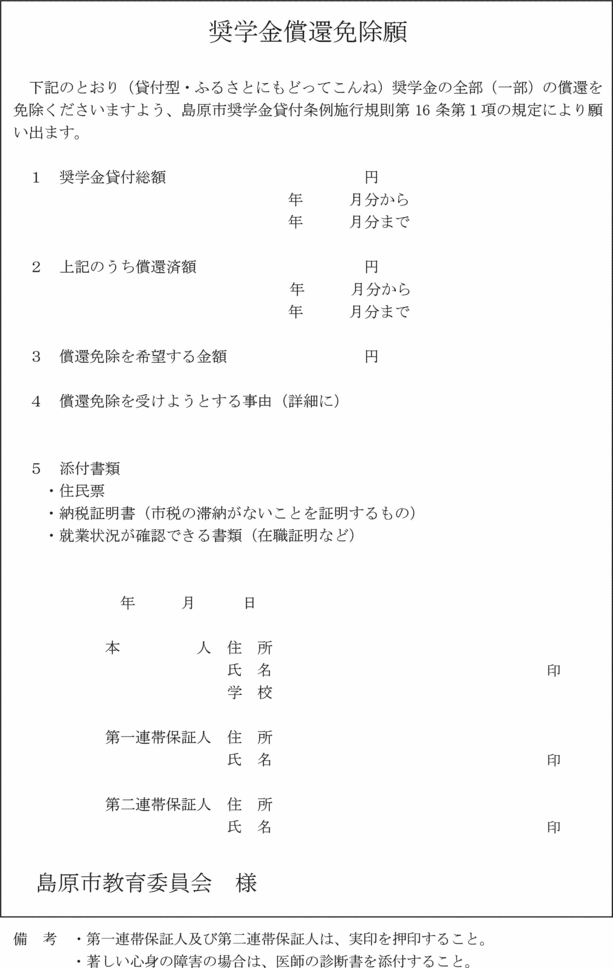
様式第20号(第16条関係)
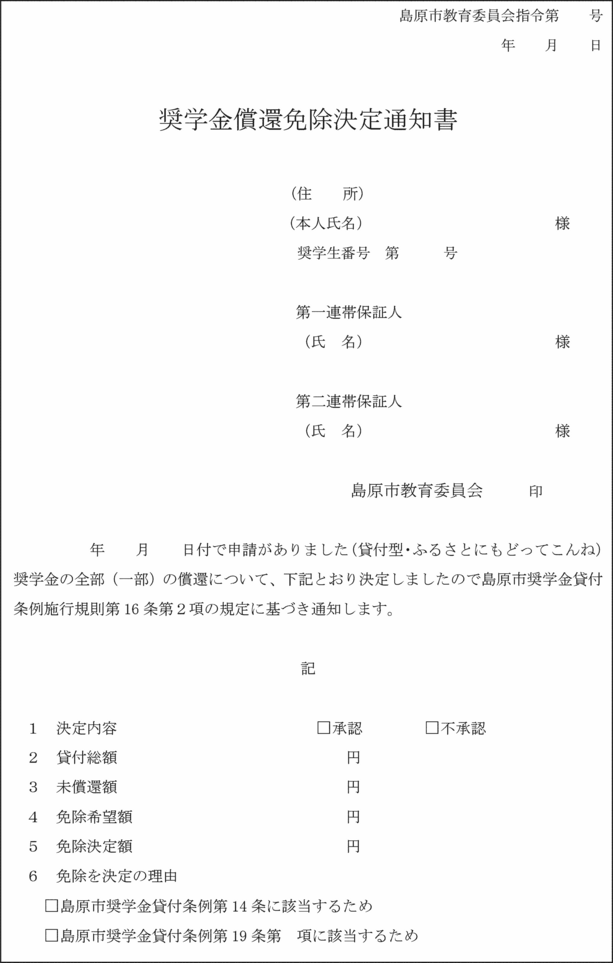
様式第21号(第17条関係)
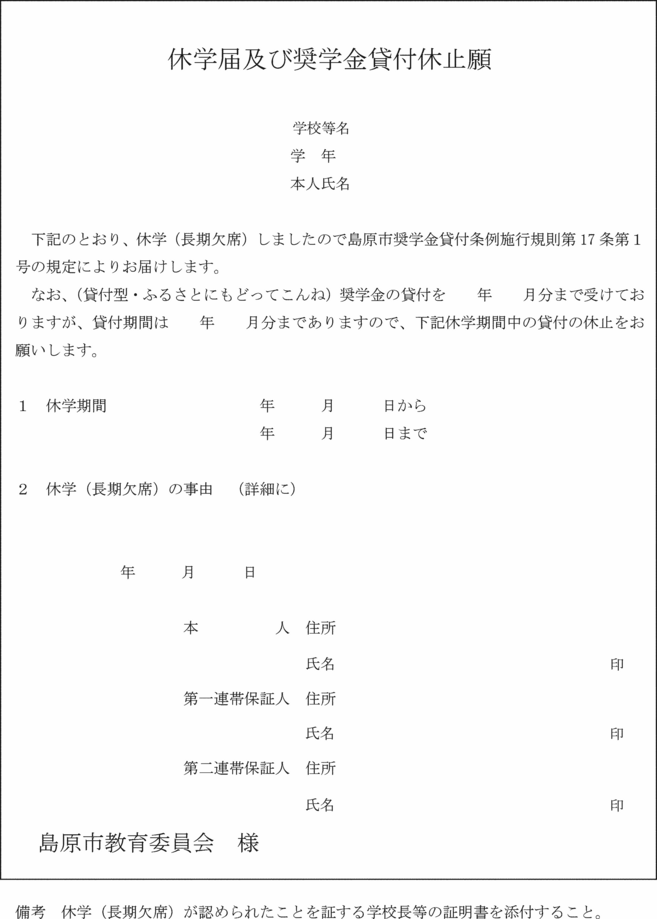
様式第22号(第17条関係)
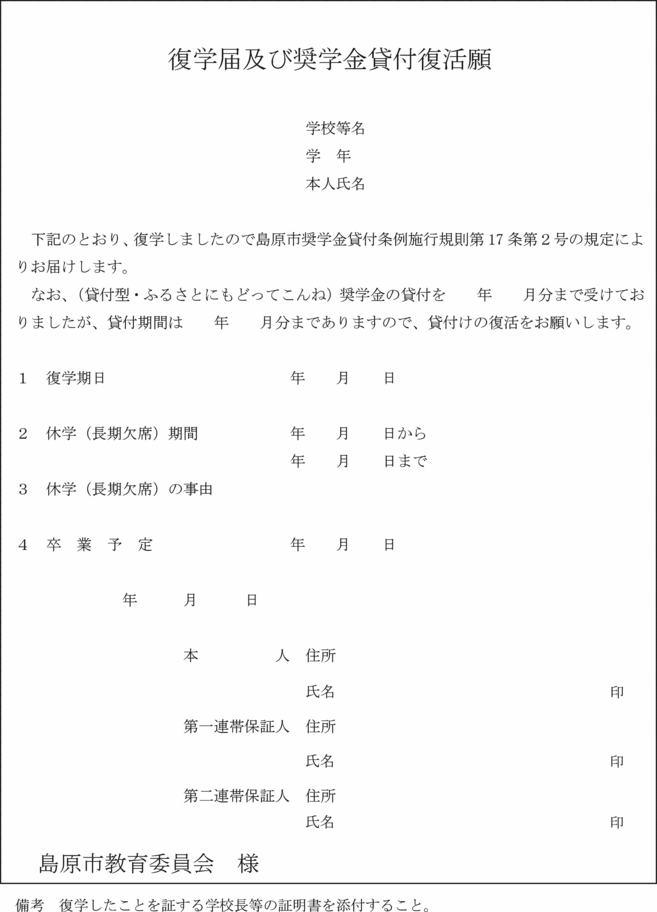
様式第23号(第17条関係)
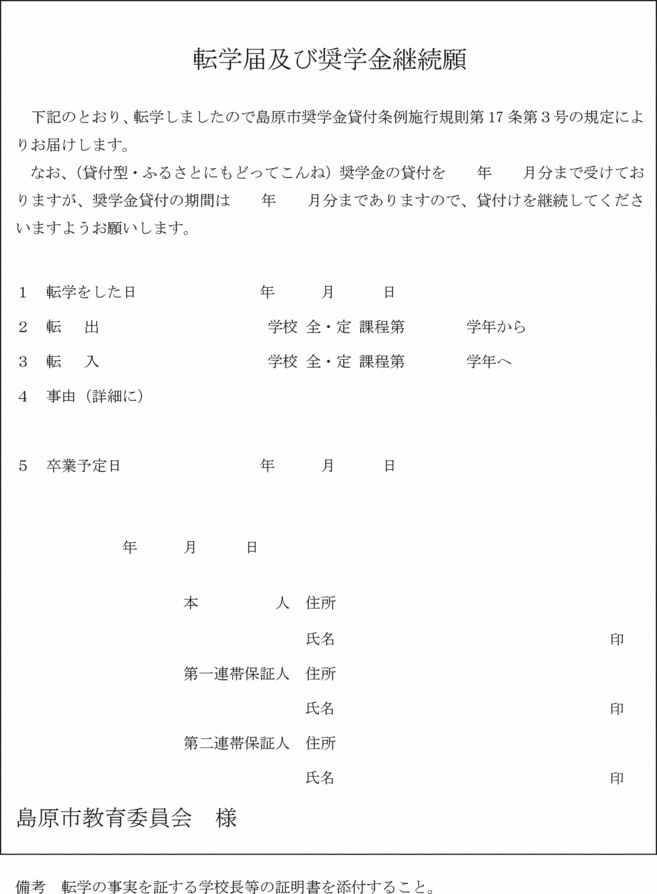
様式第24号(第17条関係)
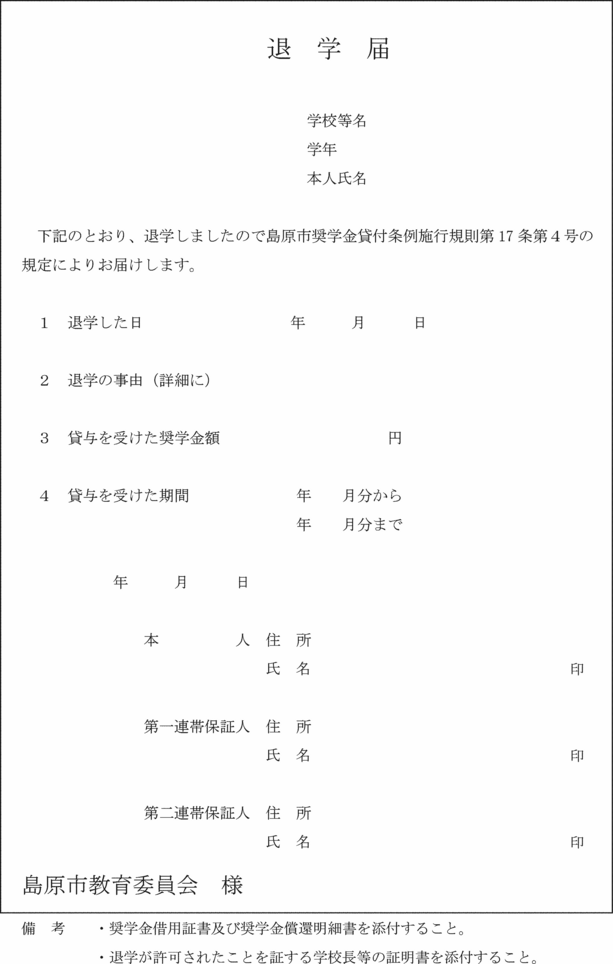
様式第25号(第17条関係)
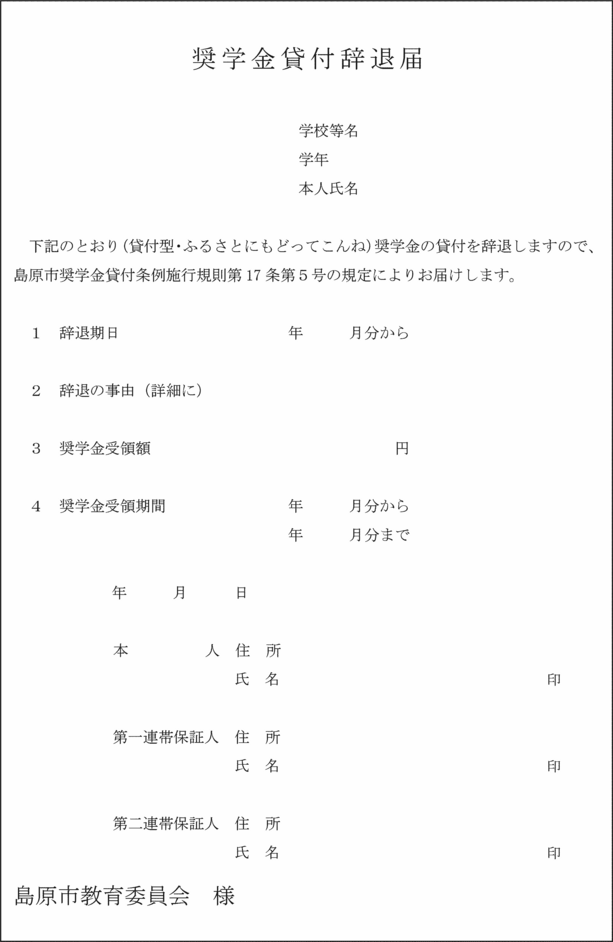
様式第26号(第17条関係)
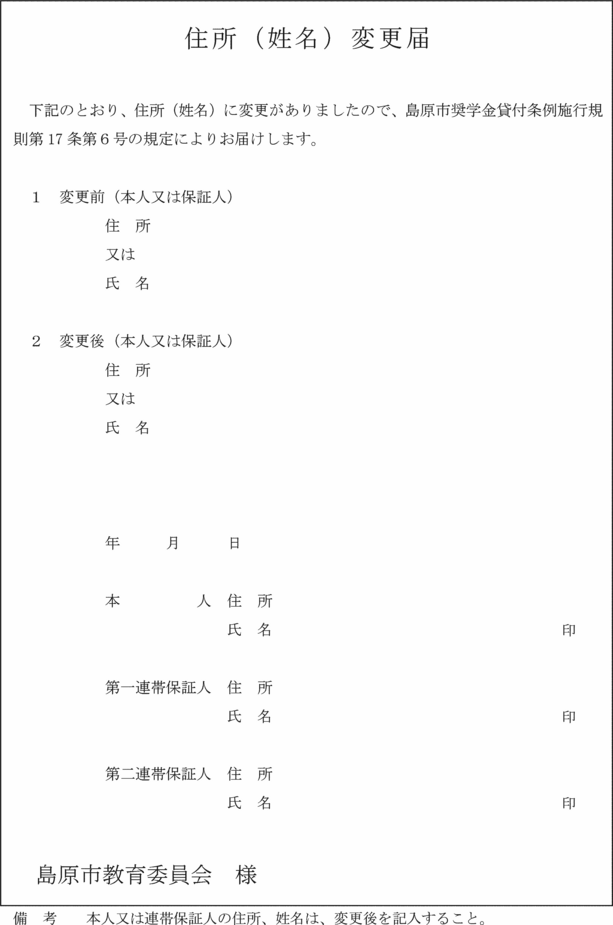
様式第27号(第17条関係)
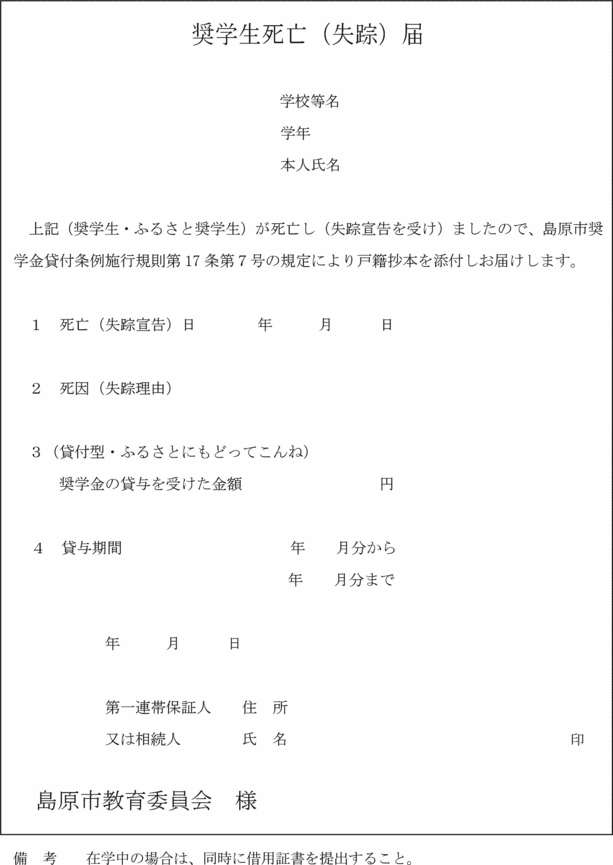
様式第28号(第17条関係)
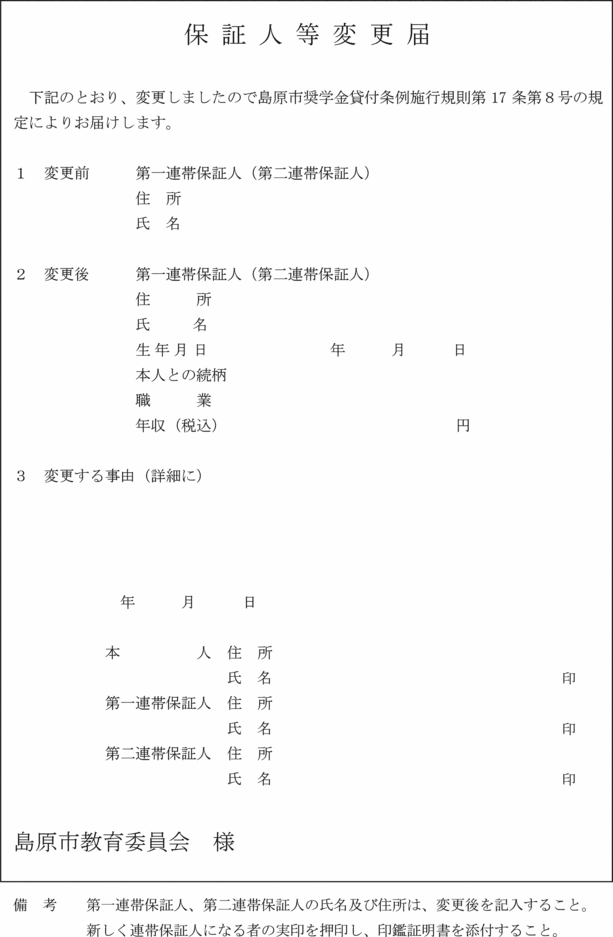
様式第29号(第17条関係)