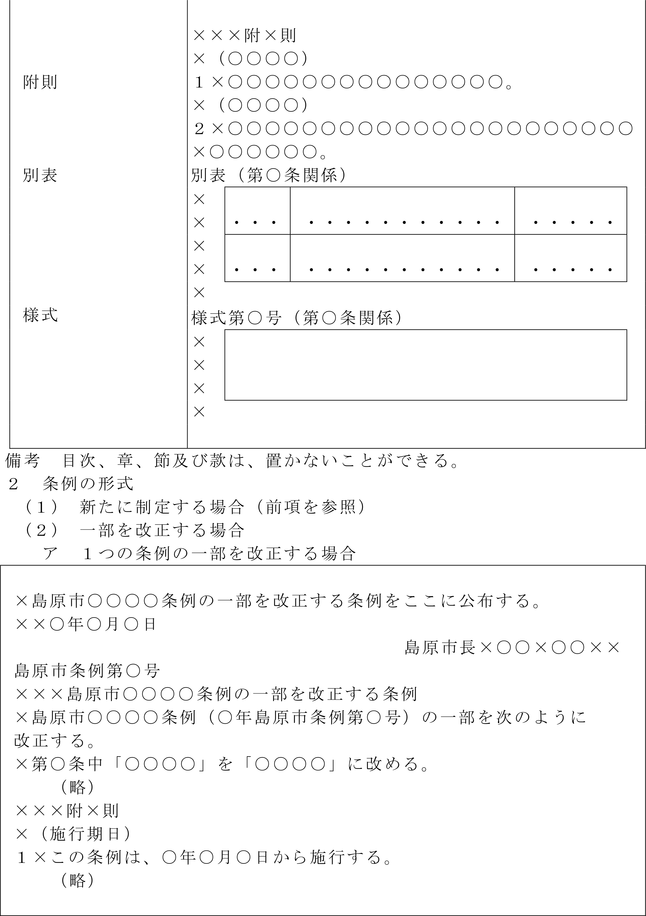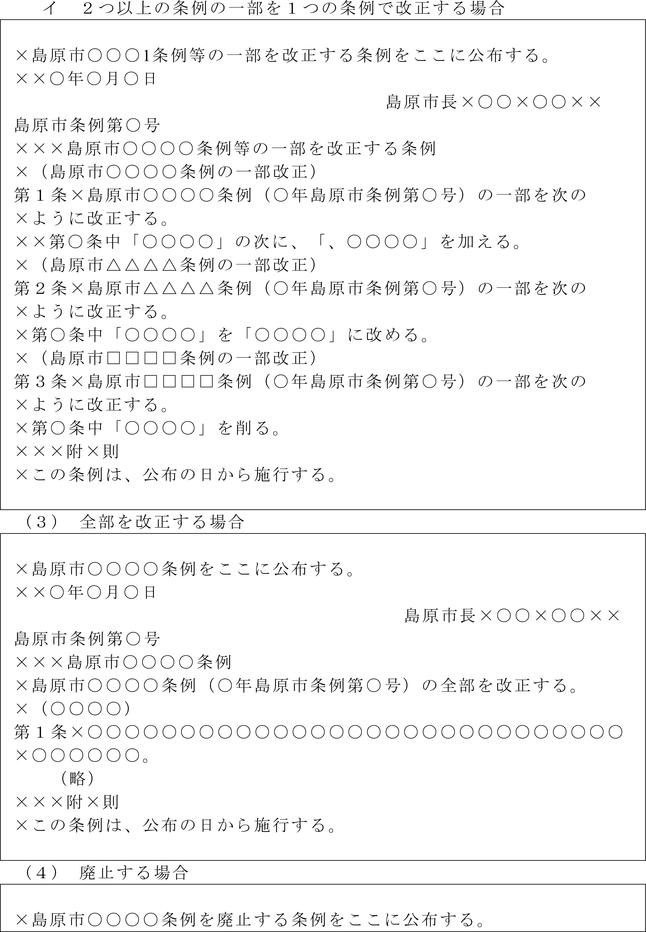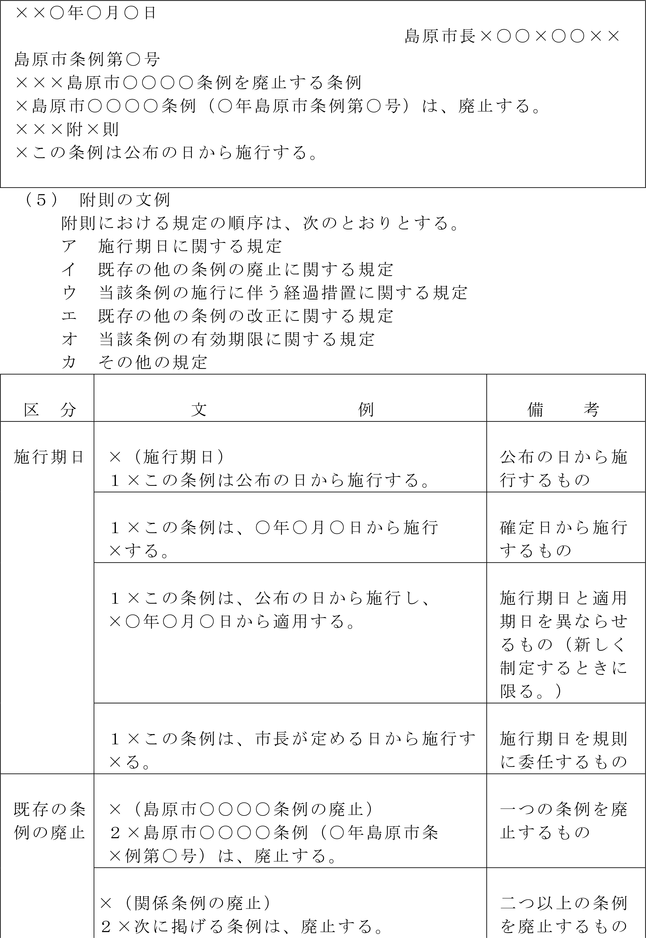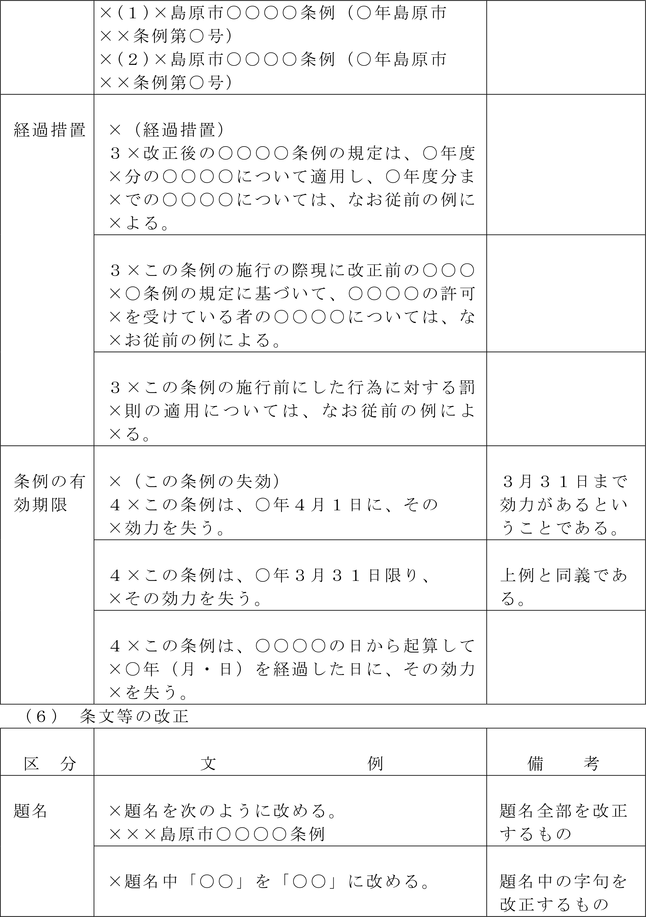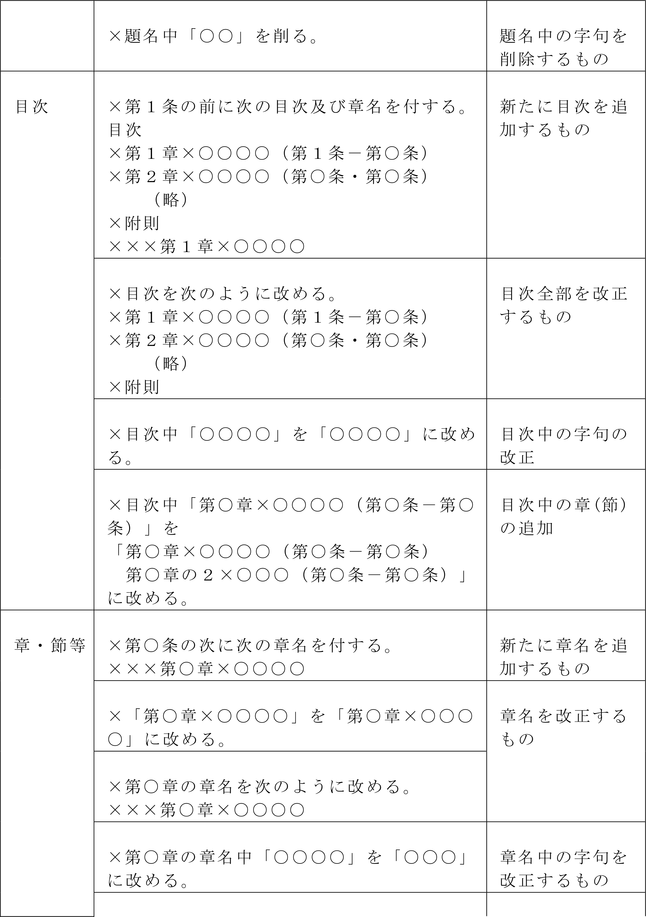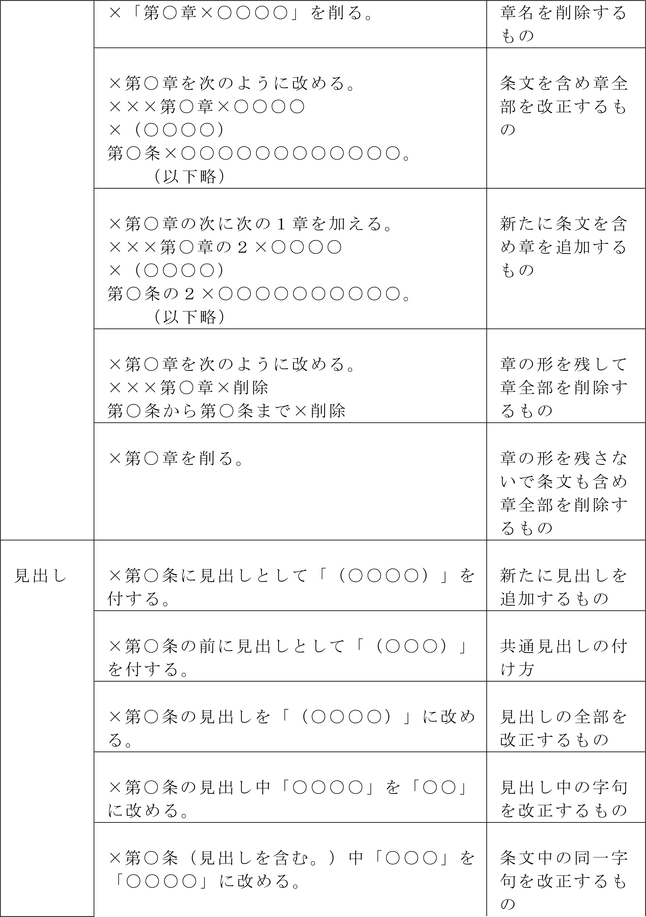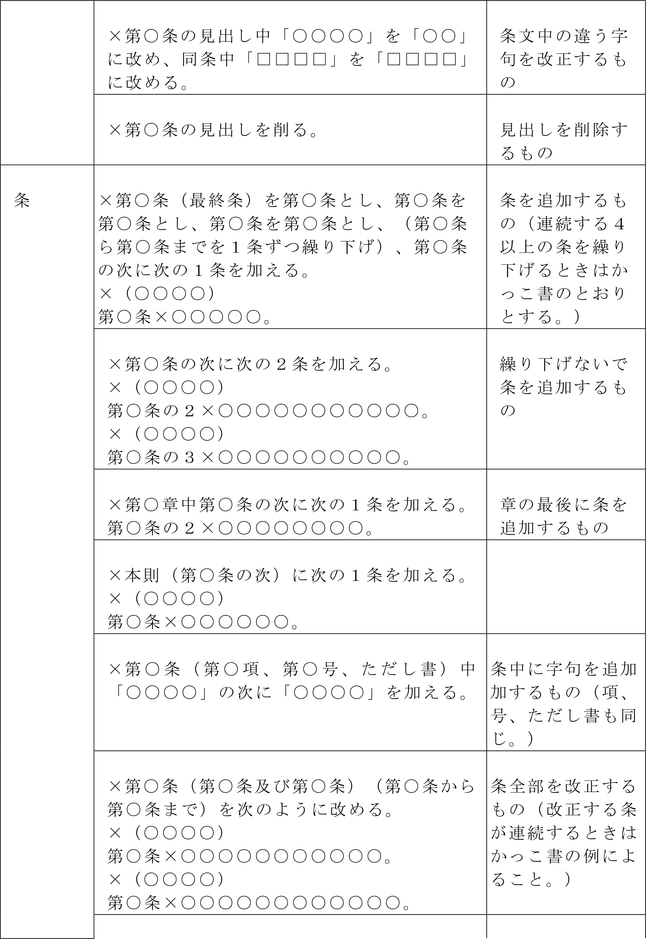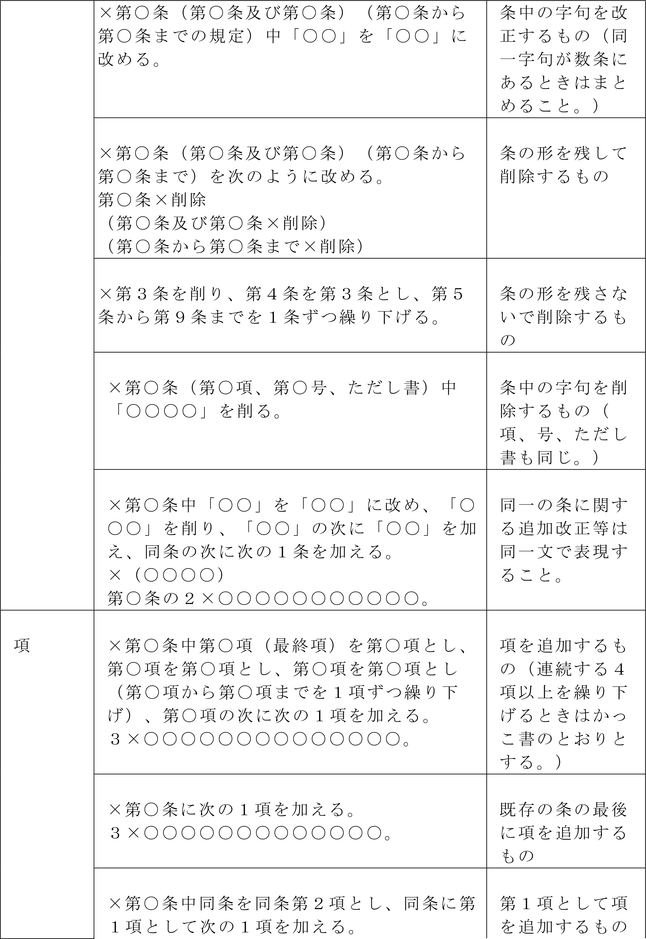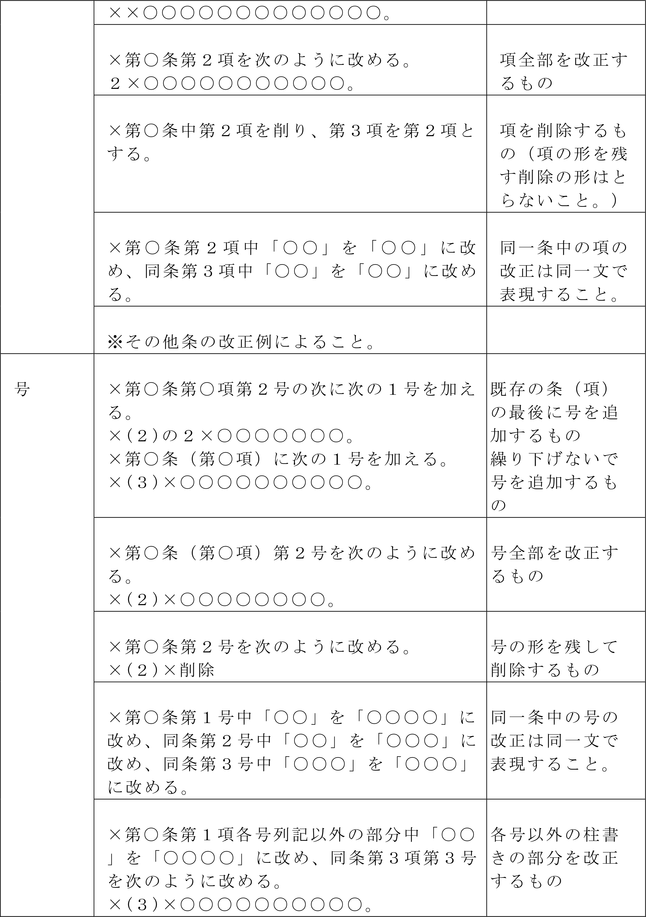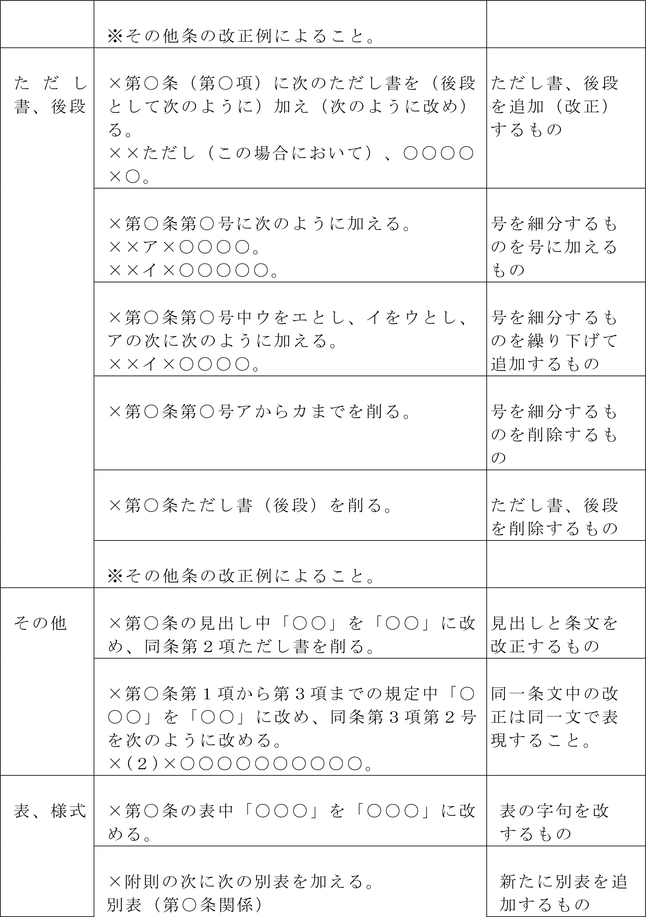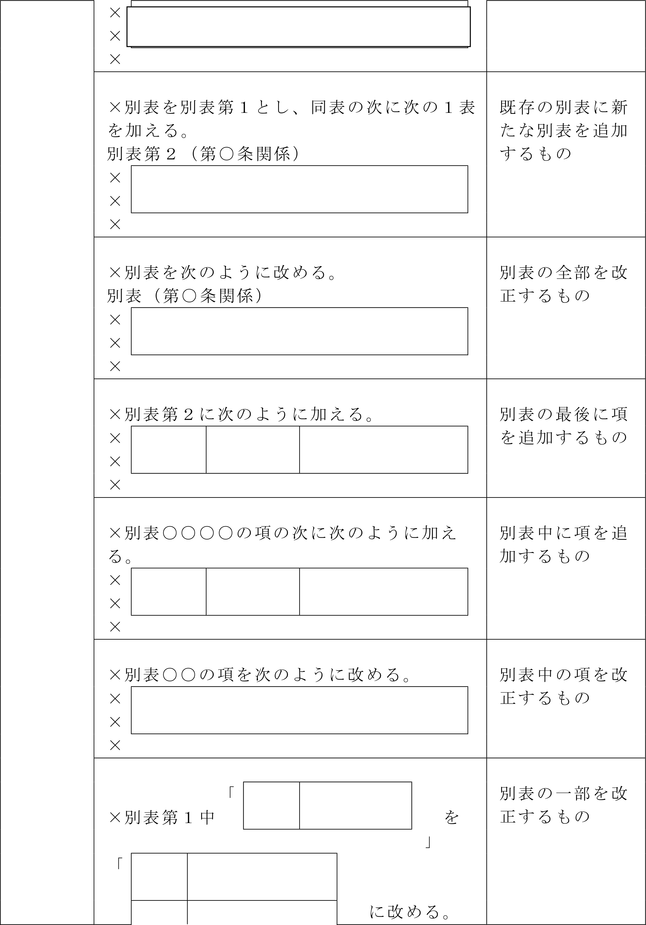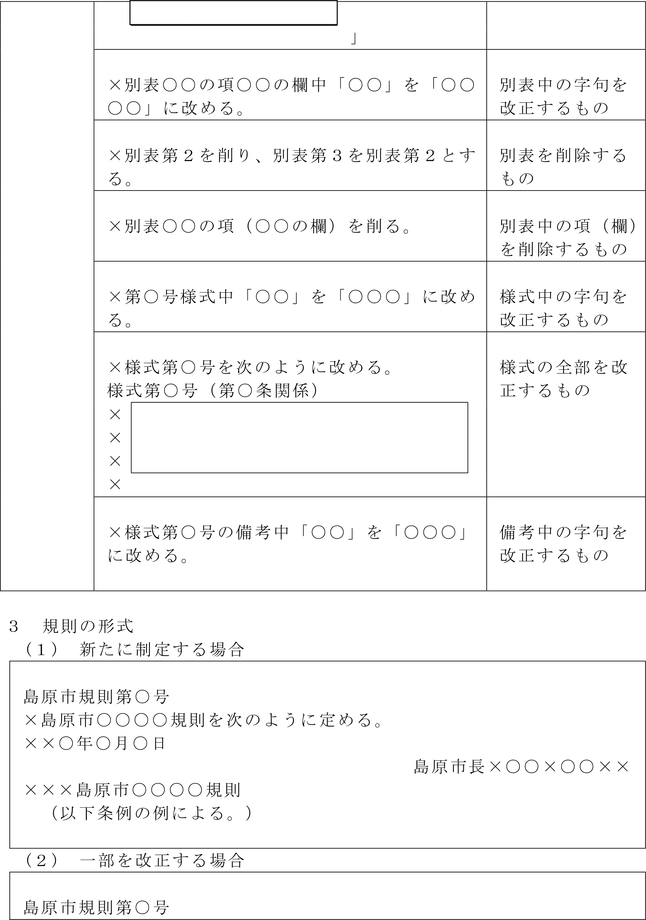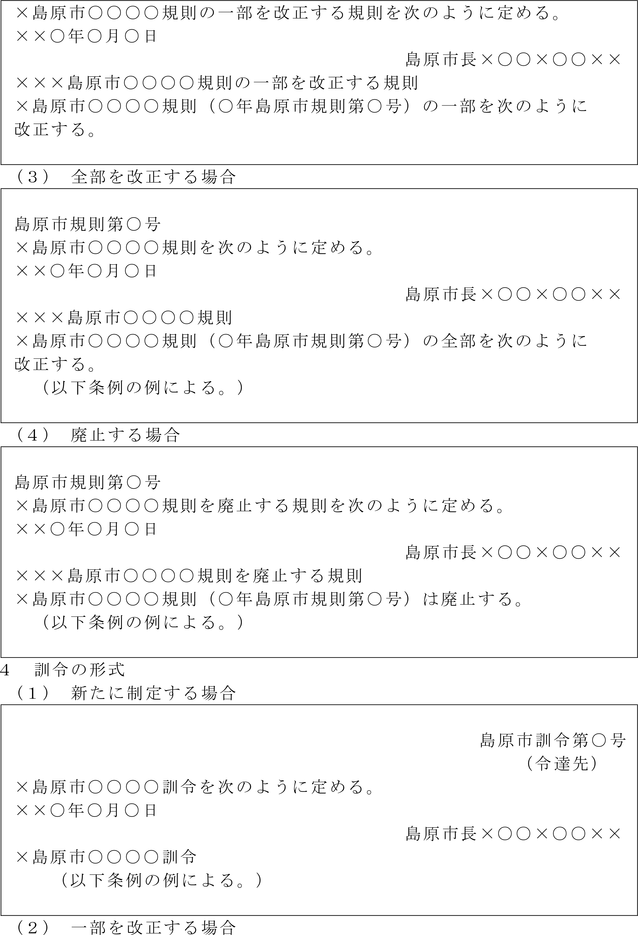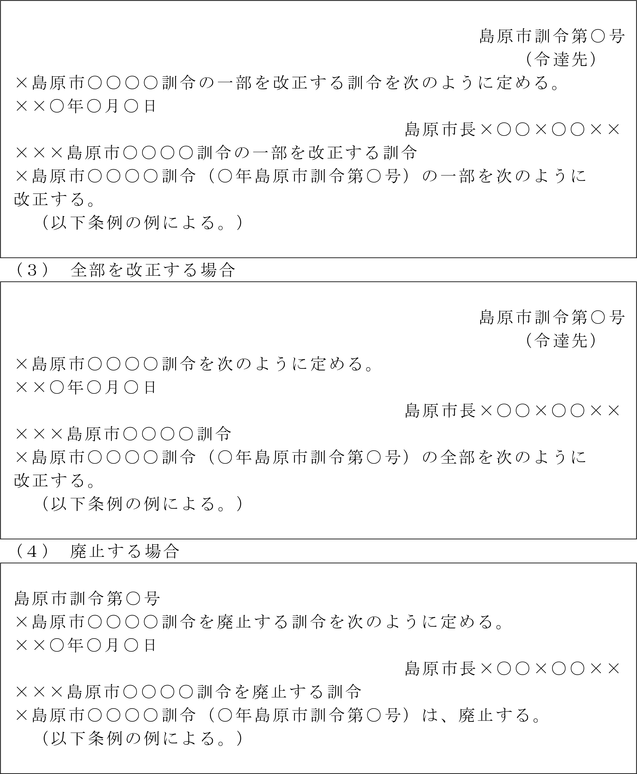○島原市公用文の取扱に関する訓令
平成30年10月19日訓令第7号
島原市公用文の取扱に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本市が用いる公用文の種類、文体、用字等について定めるものとする。
(種類等)
第2条 公用文の種類等は、次のとおりとする。
(1) 例規
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
ウ 要綱 事務を行うに当たっての基本的な事項をまとめたもの
エ 要領 事務処理の詳細な取扱についてまとめたもの
オ 規程 条例や規則など一定の目的のために定められた一連の条項の全体をいう。例規は、規程形式で作成しなければならない。ただし、要領については、箇条書きなど平易な文書で作成することができるものとする。原則として、新たに制定する例規の名称としては、用いない。(教育委員会、選挙管理委員会等の委員会規程や水道課の企業管理規程等を除く。)
(2) 公示(市が市民等に対して、例規や一定の事実等を広く周知することをいう。)
ア 公布 成立した例規の法文を公表して、一般に人が知ることができる状態におくことをいう。本市では、地方自治法第16条の規定により条例及び規則を制定した場合は、公布する。
イ 告示 法令又は権限に基づいて決定又は処分した事項を広く一般に知らせるもの。本市では、公示する根拠が法律、政令、条例若しくは規則に定められている事項、市が行った行政処分等のうち公示することにより法的効果を伴う事項又は補助金交付要綱等住民に直接関係する事務に関する要綱を制定したときは、告示する。
ウ 公告 一定の事実を広く一般に知らせるもの。本市では、公示する根拠が法律、政令、条例及び規則以外に定められている事項又は市が広く知らせる必要があると判断した事項について公告する。
(3) 令達(単なるお知らせではなく、強制力を持つもの)
ア 訓令 権限の行使及び職務について所属の職員に対して主として規程の形式をもって命令するもの
イ 指令 特定の個人又は団体の申請その他の要求に対して、権限に基づいて許可、認可、承認等の行政処分を行うもの。ただし、慣例で補助金の交付決定に使う場合もある。申請その他の要求によらず、市が一方的に行政処分を行う場合には、達という形式をとる。この場合において、指令及び達によって不利益処分を行ったときは、相手方にその処分に関する不服申立手続及び行政事件訴訟手続について、教示しなければならない。
ウ 通達 条例等の解釈、行政運用の方針、執務執行上の細目に関する事項等を指示するもの。国や県からの市への通達は、現在は廃止されたが市内部で条例の解釈や旅費の取り扱いなどについて、所管課へ確認があった場合に対する指示や不適切な経理の再発防止策の周知徹底などを全庁的に知らしめるもの
(4) 往復文
ア 照会 一定の事項について問い合わせるもの
イ 依頼 一定の行為の実現を相手に頼むもの
ウ 回答 照会、依頼等に対して返答するもの
エ 通知 特定の相手方に対して一定の事実、意思等を知らせるもの
オ 報告 一定の事実、経過、結果等を上司等に知らせるもの
カ 諮問 審議会、審査会などの諮問機関に対して意見を求めるもの
キ 答申 諮問機関がその諮問事項について意見を述べるもの
ク 建議 諮問機関が市に対し、その所管する事項を調査及び審議した結果について、自発的に意見を述べるもの
ケ 進達 申請や願などを国や県等に取り継ぐもの
コ 副申 進達する文書に参考意見を添えるもの
サ 申請 許可、認可、承認その他一定の行為を求めるもの
シ 願 一定の事項を願い出るもの。一般的には、申請を使うが入学や受験などを願い出る場合等に用いる。
ス 届 一定の事項を届け出るもの
セ 勧告 法令上定められた権限に基づいて、特定の事項について相手方に対して、一定の処置を勧め、又は促す場合に用いる。
(5) 部内関係文
ア 伺 事務の処理に当たって上司の意思決定を受けるもの
イ 復命 上司から命ぜられた任務の遂行の結果を報告するもの
ウ 内申 上司に対し、意見又は事実を伝えるもの。主として人事関係事項について使用する。
エ 供覧 文書を上司の閲覧に供するもの
オ 回覧 職員相互に参考までに見せ合うもの
カ 辞令 職員の身分、給与その他の異動についてその旨を記載して本人に交付するもの
キ 委嘱 特定の者に一定の業務の執行を委託するもの。職員に対し、職務命令として附属機関等の委員を命じる場合は、任命を使う。
(6) 契約文書
ア 契約書 申込みと承諾という相対立する2つの意思表示の合致を具体的に表示し、これを証するため取り交わすもの。主に市が行う売買、賃貸借など商取引行為で使用する。
イ 請書 軽易な内容で契約書の作成を省略する場合に主要な同意事項について確認するため取り交わすもの
ウ 協定書 2人以上の当事者が、基本的方針又は概括的事項について合意の上取り交わすもの。主に市と市以外の法人との政策協定、他の地方公共団体との災害協定、指定管理者との基本協定及び年度協定などで使用する。
エ 覚書 契約書を作成するに先立って原則的な事項を取り決め、又は契約等を取り交わす場合に、合意を得る過程において生じた重要な事項を取り交わすもの
オ 念書、誓約書 一方の当事者が、相手方にあることを確認し、又は義務を負担することを明らかにするために取り交わすもの
(7) 挨拶文
ア 式辞 市が主催者のとき、式典の始めにその式典の意義などを述べる場合に用いる。
イ 祝辞 市が式典に招かれたとき、その式典を祝う言葉を述べる場合に用いる。
ウ 弔辞 葬儀などに際し、個人の生前の業績をたたえ、その死を悼み弔う場合に用いる。
(8) その他
ア 議案文 議会等の会議において議決等をすべき事件について、その会議の審議を求めるために提出するもの
イ 宣言文 観念又は意見を広く一般に表示するもので、法的効果を持たないもの
ウ 事務引継文 職員が退職、異動等に伴い、前任の職員が担任していた事務処理状況を後任又は所属長が指定する職員に引き継ぐもの
エ 証明文 一定の事実を明らかにするもの
オ 賞状 展覧会等で優秀な成績を収めた者を賞するもの
カ 書簡文 郵便物等として案内状、礼状、あいさつ状等に用いられるもの
キ 陳情文・請願文 市に実情を述べて、適切な処置を要望するもの。一般的に法令等に基づかず要望をなすものを陳情、法令等に基づき所定の形式、手続きに則って要望をなすものを請願という。
ク その他職員が職務上作成するもの
(書き方)
第3条 公用文は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公庁が特に様式を縦書きと定めているもの
(3) 広報紙
(4) 賞状、表彰状、感謝状、式辞、祝辞、弔辞その他これらに類するもののうち、縦書きが適当と認められるもの
(文体)
第4条 公用文の文体は、口語体で書き表し、「ます」体を用いる。ただし、例規、令達、辞令、契約文書、議案文その他これらに類するものについては、「である」体を用いる。
2 公用文の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 文語体の表現は、なるべく、日常一般に使われている平易な言葉を使用すること。
(2) 形式、内容いずれも統一性のある文章の作成に努め、文が長い場合は、短く区切り、又は箇条書きにすること。
(3) 文章の飾り、あいまいな言葉又は回りくどい表現は、避けること。
(漢字)
第5条 漢字は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の範囲内で用いるものとする。ただし、固有名詞及び専門用語で、特別な漢字の使用を必要とするものについては、この限りでない。
2 例規で使用する漢字は、法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)によるものとする。
(仮名)
第6条 仮名は、原則として、平仮名を用いる。
2 外国の地名及び人名並びに外来語及び外国語は、片仮名を用いる。ただし、外来語でも「たばこ」、「かるた」等のように、外来語の意識が薄くなっているものは、ひらがなで書くことができる。
例 ガス ガラス ビール アルコール ボタン
(仮名遣い)
第7条 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとし、特に「じ・ず」及び「ぢ・づ」の遣い方については、次の各号に定めるものとする。
(1) 原則として、「じ・ず」を用いる。
(2) 次のような場合には、「ぢ・づ」を用いる。
ア 同音の連呼の場合
例 ちぢむ(縮む) つづみ(鼓) つづく(続く)
イ 二語の連合によって生じる場合
例 はなぢ(鼻血) まぢか(間近) みかづき(三日月)
(送り仮名)
第8条 送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によるものとする。
(数字)
第9条 数字は、第4号に掲げる場合を除いてアラビア数字を用い、次の事項に留意する。ただし、縦書き文書に用いる数字は、原則として漢数字とする。
(1) 数字の区切り方
3位区切りとし、区切りには、コンマ「,」を付ける。ただし、年号、文書番号、電話番号等のように特定の対象を示すために用いる場合は、区切りを付けない。
例 1997年 第1234号 0957-63-1111
(2) 小数、分数及び帯分数
例 小数 0.58(小数点には、「.」を付ける。)
分数  又は3分の1
又は3分の1
 又は3分の1
又は3分の1帯分数 2 (21/4とは書かない。)
(21/4とは書かない。)
 (21/4とは書かない。)
(21/4とは書かない。)(3) 日付、時刻及び時間
例 日付 平成9年1月1日 1997年3月31日
時刻 9時 3時15分
時間 24時間 2時間30分
(4) 漢数字を用いる場合
ア 数の概念を離脱した熟語
例 一般 十分に
イ 固有名詞
例 九州 五島 三会町
ウ 慣用的な語
例 二言目(ふたことめ) 三月(みつき) 一休み(ひとやすみ)
エ 概数を示す場合
例 四、五日 数十日
オ 単位として用いる語
例 300万人 50億円
(5) 数字で年月又は期間を表す場合、期間の月と暦の月と混同されるときは、「か」又は「箇」を用いる。
例 3か月 6箇月
(見出し符号)
第10条 見出し符号は、文章の項目を細別する場合に、次のように用いる。ただし、項目が少ない場合は、「第1」を省いて「1」を用いる。
第1
1
(1)
ア
(ァ)
a
(a)
2 条例等の場合は、次のように用いる。
第1条
1
(1)
ア
(くぎり符号)
第11条 くぎり符号は、文章の構造、語句の関係を明らかにする場合に、おおむね次の各号に定める用法で用いる。
(1) 「。」(まる)-句点 一つの文章の終わるところに用いる。ただし、次の点に注意する。
ア 「 」や( )の中の文章の終わりに用いる。
例 島原市名誉市民(以下「名誉市民」という。)・・・
イ 名詞形で終わる文章には用いないが、名詞形の後に更に文章が続くとき又は名詞形が「とき」若しくは「こと」で終わるときには、名詞形の語句の後に用いる。
例 禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、その執行を終わったものを除く。
(2) 「、」(てん)-とう点 文章の中で、言葉の切れ続きを明らかにする必要があるところに用いる。ただし、次の点に注意する。
ア あまり多く用いると、かえって文全体の関係が不明になることがある。
イ 文の初めに置く接続詞及び副詞の後に用いる。
例 なお、 ただし、 したがって、 たとえ、
ウ 語と語を接続する「かつ」の前後には用いないが、語句と語句を接続する「かつ」の前後には用いる。
例 必要かつ十分 通知し、かつ、これを公表する
エ 限定、条件などを表す語句の後に用いる。
例 ので、 ため、 のほか、 限り、
オ 目的格の助詞の「を」、「に」及び「と」の後では用いないが、条件句がはいる場合は、目的格の助詞の後に用いる。
例 幹事若干人を置く。
・・・監査委員を、議会の同意を得て、選任する
カ 対句の場合は、対句の区切にのみ用いて、対句の中にある主語の後には用いず、対句を受ける述語の前にも用いない。
例 都道府県にあっては総務大臣に、市町村にあっては都道府県知事に届け出なければならない。
(3) 「.」(ピリオド) 単位を示す場合又は省略符号として用いる。
ア 単位を示す場合に用いる。
例 0.005
イ 省略符号として用いる。
例 P.T.A H30.10.1
(4) 「・」(なかてん)
ア 名詞を並列する場合に、「、」の代わりに又は「、」とあわせて用いる。
例 小・中学校、高等学校
イ 外国の国名、人名等の区切りに用いる。
例:グレート・ブリテン
(5) 「:」(コロン) 次に続く説明文やその他の語句があることを示す場合又は時分を省略する場合に用いる。
例 場所:島原市役所会議室 午後3:30
(6) 「~」(なみがた) 「・・・から・・・まで」を示す場合に用いる。
例 島原~東京
(7) 「-」(ダッシュ) 語句の説明、言い換え及び丁目、番又は号を省略する場合に用いる。
例 ガット-関税と貿易に関する一般協定 島原市桜町2-22
(8) 「( )」(括弧) 語句に注釈を付ける場合又は条例等の条文の見出しを表示する場合に用いる。
例 児童(2歳未満は除く。)
(9) 「「 」」(かぎ括弧) 言葉を定義する場合又は他の語句若しくは文章を引用する場合などに、引用する語句等を明示するために用いる。
例 この規則において「職員」とは、市長部局の職員をいう。
(10) 「『 』」(二重かぎ括弧) かぎ括弧の中で、更に引用等が必要な場合に用いる。ただし、例規には、使用しない。
(11) 「→」(矢印) 左の語句が右の語句に変わることを示す場合などに用いる。
例 煙草→たばこ
2 繰り返し符号
(1) 「々」 同じ漢字1字が続く場合に用いる。ただし、続く漢字が異なる意味では用いない。
例 人々 国々 協議会会長 民主主義
(2) 「〃」 表、台帳、帳簿などで同一であることを示す場合に用いる。
3 次に掲げる符号は、おおむねそれぞれに定める用法で用いる。
(1) 傍線及び傍点 語句の強調又は注意のためのもの
例 会議場所:第3会議室 平成2年度まで
(2) 「・・・」(点線) 語句の代用のもの
例 ・・・から、・・・・まで
(使用する用紙)
第12条 用紙は原則として、日本工業規格A4判を縦長に用いる。
(文書のとじ方)
第13条 文書は、左とじとする。ただし、特別な場合の文章のとじ方は、次の例による。
(1) 縦書き文章のみをとじるときは、右とじとする。
(2) A4判用紙を横長に用いるときは、上とじとしてもよい。
(条例等の書式)
第14条 例規及び訓令の書式については、別表のとおりとする。
附 則
この訓令は、発令の日から施行する。
別表(第14条関係)