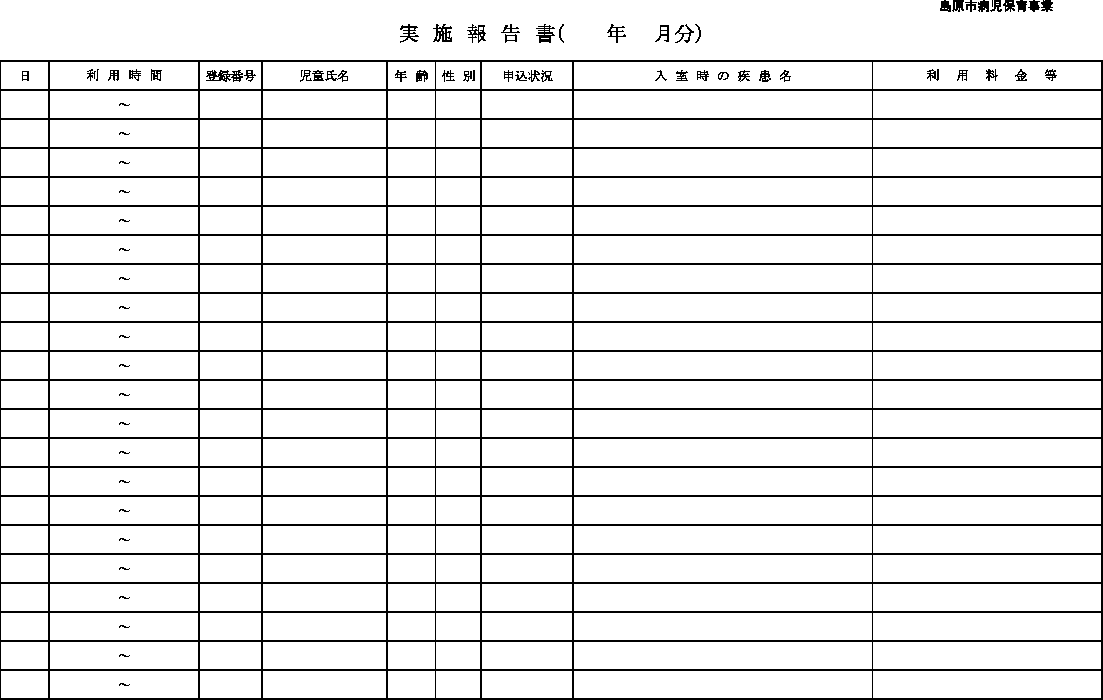○島原市病児保育事業実施要綱
令和4年2月1日告示第8号
島原市病児保育事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が行う病児保育事業を実施するに当たり、「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙病児保育事業実施要綱に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、島原市(以下「市」という。)とする。
(事業の実施)
第3条 市長は、当該事業を実施するため、地域の状況、施設の保育環境及び保健医療体制等を勘案して、医師との緊密な連携及び適切な処遇が確保される施設を有する医療法人等に事業を委託することができる。
(利用対象児童)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児」という。)は、次に掲げる病気(以下この条において「病気」という。)の回復期に至らない場合で当面症状の急変が認められないとき又は病気の回復期にある場合で、かつ、保護者の勤務の都合等により家庭での保育が困難な場合に、事業を利用する必要性がある市内に住所を有する小学校6年生までの児童とする。
(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等乳幼児が日常罹患する疾病
(2) 麻しん、水痘、風しん等の感染症疾患
(3) 喘息等の慢性疾患
(4) 熱傷等の外傷性疾患
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、対象児童とすることができる。
(実施施設)
第5条 当該事業の実施施設(以下「実施施設」という。)は、病院、診療所等に付設された次の各号に掲げる要件を備えた施設であって、事業を必要とする児童に対し適切な処遇が確保されると認められる施設とする。
(1) 利用定員を4人以上とすること。
(2) 次の要件を満たす保育室、観察室(安静室)、調理室及び調乳室を有すること。
ア 保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1.98㎡以上とし、1室80㎡を下回らないこと。
イ 観察室(安静室)の面積は、原則として利用定員1人当たり1.65㎡以上とし、乳幼児の静養又は隔離の機能を持つものであること。
ウ 調理室は専用とすること。ただし、病院、診療所等の本体施設等の調理室と兼用しても差し支えない。
エ 調乳室は専用とすること。ただし、専用の調乳室が設けられない場合は、調理室等の一部を調乳室として区画すること。なお、病院、診療所等の基準に抵触しない範囲において、共用施設を充てても差し支えない。
(3) 児童の看護を専門に担当する職員として、看護師、准看護師、保健師又は助産師を利用児童おおむね10人につき1人以上配置するとともに、児童が安心して過ごせる環境を整えるために保育士を利用児童おおむね3人につき1人以上配置すること。
(4) 医師の配置及び医療機関との協力体制等を常時確保すること。
(事業の利用時間等)
第6条 事業の利用時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
土曜日 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
3 事業は、原則として7日間連続して利用することができる。ただし、児童の健康状態についての医師の判断又は保護者の状況により、市長が必要と認めるときは、7日を超えて利用することができる。
(事業の休日)
第7条 事業の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日
(4) その他市長が適当と認める日
(利用手続等)
第8条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、利用登録書兼同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による利用登録書が提出されたときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、児童の保護者に通知するものとする。
4 第1項の手続は、特に緊急を要する場合は実施施設を経由して行うことができるものとする。
5 対象児の送迎は原則として、保護者が行うものとする。
6 保護者は、利用期間中は常に連絡先を明らかにしておくとともに、次条に該当した場合は、直ちに児童を実施施設から引き取るものとする。
(利用の制限)
第9条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、病児保育の利用を拒否し、又は利用を中止させることができる。
(1) 伝染性の疾患を有し、感染のおそれがあると、実施施設の指定した医師が判断したとき。
(2) 病状が重く、入院治療の必要があると、実施施設の指定した医師が判断したとき。
(3) 受入れを認めると定員を超える場合等、病児保育の実施体制の維持が困難と判断したとき。
(4) 保護者が実施施設の指導に従わなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施施設の利用が適当ではないと認めたとき。
(保育の内容)
第10条 実施施設の長は、児童の状態に応じて安静度を判断し、その状態に応じて観察の実施又は隔離室の利用を図るものとする。
(保健管理)
第11条 実施施設の長は、児童への保健管理にあたっては、日々の病状の記録、家庭との連絡等を適正に実施しなければならない。
2 実施施設の長は、従事職員に対する養護、救急蘇生等の理解について研修に努めるものとする。
(安全管理)
第12条 実施施設の長は、通常の保育における安全管理に加え事業の特殊性に鑑み、児童の健康管理及び事故の発生防止等に特に留意するものとする。
(事故発生時の報告義務)
第13条 実施施設は、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を市長に報告しなければならない。
(事業の停止)
第14条 実施施設は、次の事由が生じたときは、市長と協議のうえ事業を停止することができる。
(1) 事業従事者が、感染症疾患にかかったとき。
(2) 実施施設内で、対象児を保育することが適当でないと認められる事由が発生したとき。
(病児保育日誌)
第15条 実施施設は、対象児に対し事業を提供したときは、対象児童ごとに病児保育日誌(様式第4号。以下「日誌」という。)を3部作成しなければならない。
2 実施施設は、前項の規定により作成した日誌について、1部を保管し、1部を対象児の引き取り時に保護者に交付し、1部を市長に提出しなければならない。この場合において、日誌の市長への提出は、1か月分をまとめて行うものとする。
(費用)
第16条 保護者は、事業を利用したときは、別表に定める費用を実施施設に支払うものとする。
2 実施施設で要した医療費等の費用については、保護者が実費を負担するものとする。
(医療機関との連携)
第17条 実施施設は、指導医、近隣の医療機関と十分連携を図るものとする。
(経理処理)
第18条 実施施設は、事業に係る収入及び支出について、他の事業の経理と区別し収支を明確にしておかなければならない。
2 実施施設は、帳簿を完備し5年間保存するものとする。
(事業の実績報告)
第19条 実施施設は、事業が完了したときは、実施報告書(様式第5号)を事業完了後30日以内に、市長に提出しなければならない。
2 実施施設は、事業の委託期間終了後、収支決算書を提出しなければならない。
3 実施施設は、職員の雇用に係る書類を提出しなければならない。
(調査)
第20条 市長は、必要に応じ実施施設の事業に関する運営状況及び財産状況並びに会計帳簿その他の関係書類を調査することができる。
(改善命令)
第21条 市長は、実施施設の事業運営が不適当であると認めたときは、実施施設に対しその改善を命じることができる。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年8月25日告示第97号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第16条関係)
区分 | 費用(利用料) |
生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 ただし、連続3日以上利用の場合は1日につき1,000円とする。 | 2,000円 (1,000円) |
様式第1号(第8条関係)
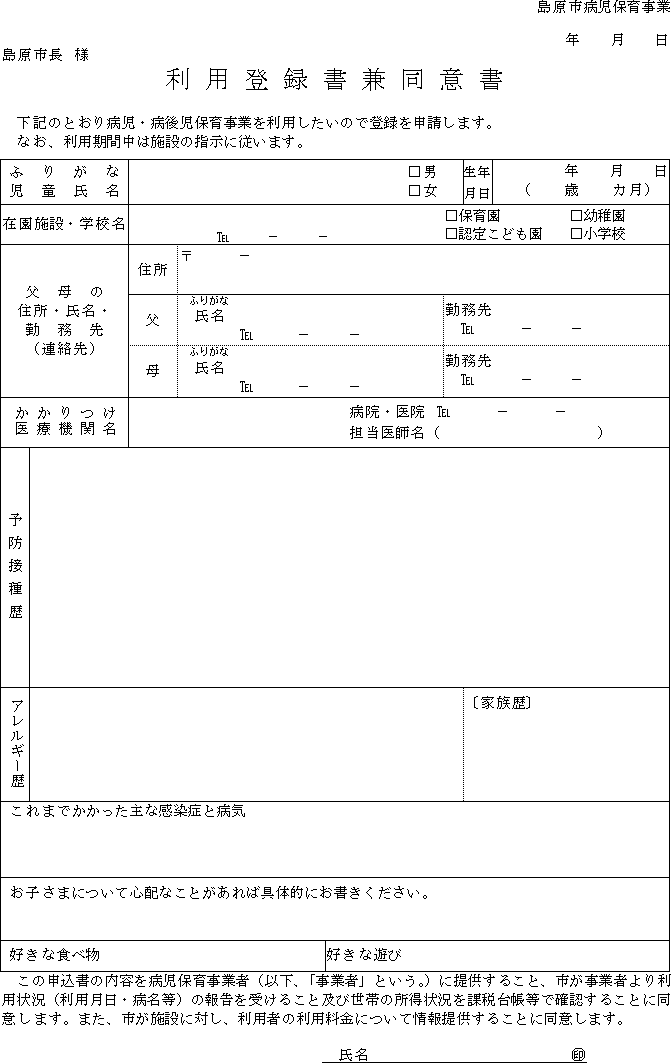
様式第2号(第8条関係)
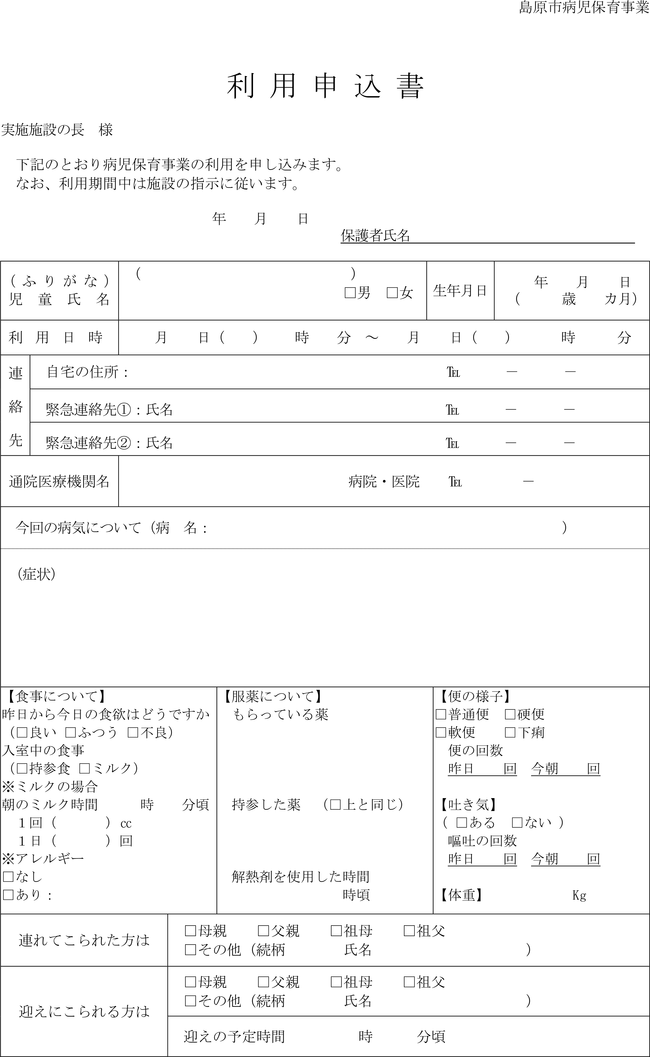
様式第3号(第8条関係)
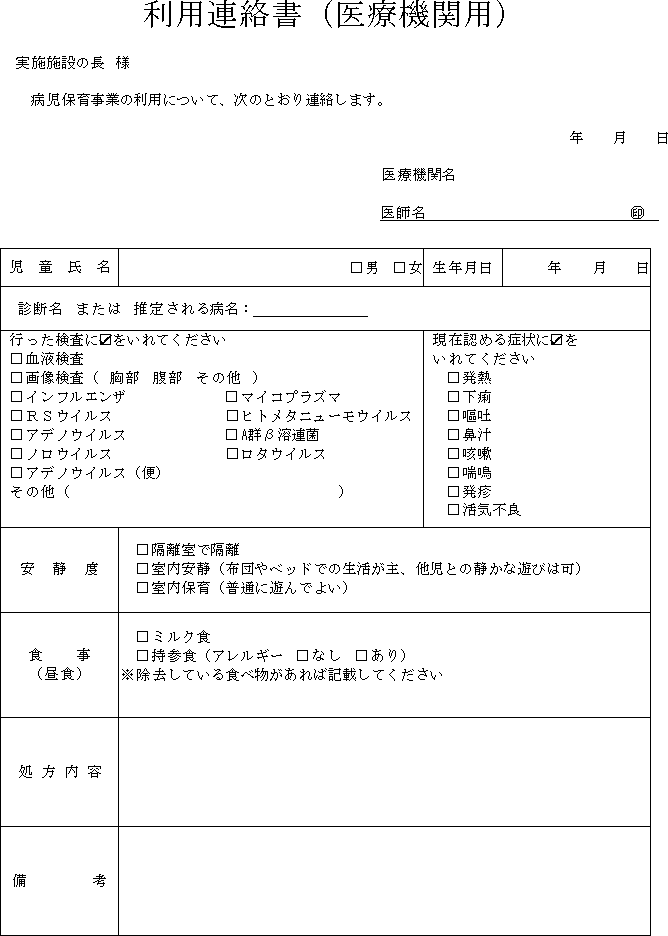
様式第4号(第15条関係)
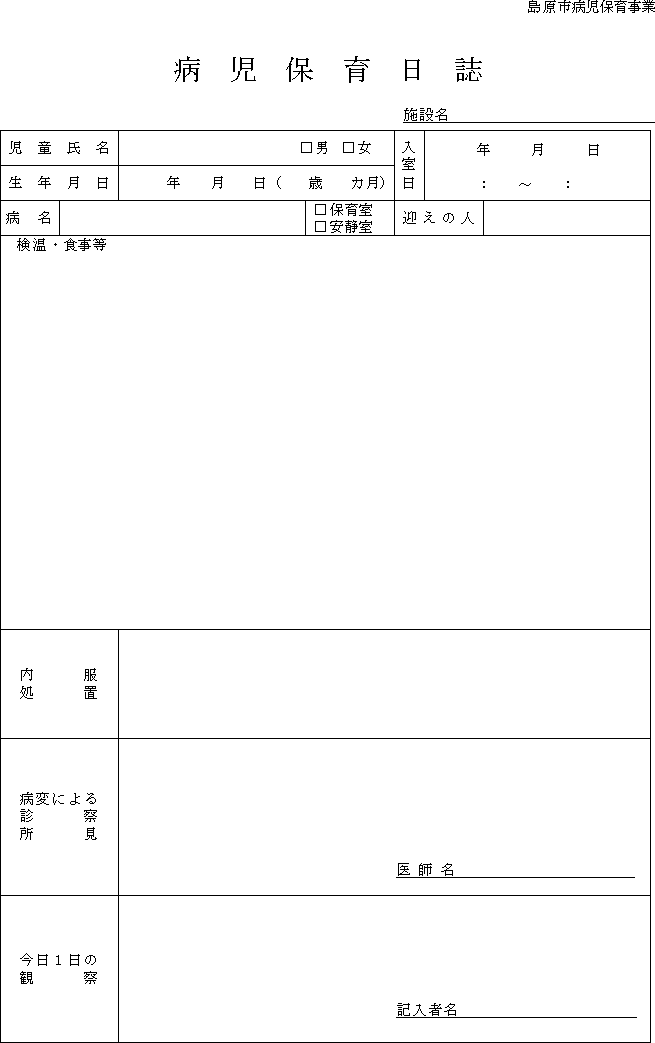
様式第5号(第19条関係)